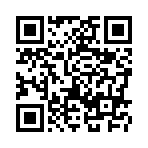2014年01月30日
はしご車 その1
お久しぶりです。今回は予告通り「はしご車」の特集です。なお、写真の関係上今回はその1とさせていただきます。
はしご車とはご存じの通り、高層階での災害に対応する車両です。主にビル火災などの消火・救助を任とし、山岳救助や水難救助で使用している自治体もあります。また、屈折放水車や屈折はしご車などもはしご車の分類に含まれます。
はしごの長さもそれぞれで、短いものは15m級、長いものは50m級と幅は広いです。また、使用頻度も低いためベースとなっている車両も一世代や二世代前の車両が使われている自治体が多いです。なお今のはしご車はほとんどがはしご車専用車体を使用しており、ほとんど自治体が同じタイプのはしご車を使用しています。

こちらは浜松市消防局のはしご車。15m級の小型はしご車で、3階などの建物火災などに対応します。

こちらは大月市消防本部のはしご車。現在はすでに更新されていますが、このように古いタイプの車両も居たりします。昔のタイプの車両はバケットが脱着式だったため、使用する際に取り付けて使用していました。

こちらは都留市消防本部のはしご車。1978年導入のはしご車で今もまだ現役です。

三菱のグレートをベースとしたはしご車。南アルプス市消防本部のはしご車で、今のはしご車同様にバケットを搭載した状態での収納ができます。

こちらは磐田市消防本部のはしご車。2013年度で更新されてしまいますが、バケット後付タイプの30m級はしご車です。

こちらは今は無きいすゞ810がベースのはしご車。熱海市消防本部の車両で、35m級のはしご車になります。ホテルが多い熱海市だからこその車両かもしれません。

こちらは新潟市消防局のはしご車。日野プロフィアがベースの車両で、50mの高さまで伸ばせるはしごを搭載しています。
なお、現在国内で最大級のはしご車は地上高54mまで伸ばすことが出来ます。
以上で、はしご車 その1を終わります。その2では、はしご車専用車体を使用した車両やクレーン専用車体を利用した車両を紹介します。では
はしご車とはご存じの通り、高層階での災害に対応する車両です。主にビル火災などの消火・救助を任とし、山岳救助や水難救助で使用している自治体もあります。また、屈折放水車や屈折はしご車などもはしご車の分類に含まれます。
はしごの長さもそれぞれで、短いものは15m級、長いものは50m級と幅は広いです。また、使用頻度も低いためベースとなっている車両も一世代や二世代前の車両が使われている自治体が多いです。なお今のはしご車はほとんどがはしご車専用車体を使用しており、ほとんど自治体が同じタイプのはしご車を使用しています。

こちらは浜松市消防局のはしご車。15m級の小型はしご車で、3階などの建物火災などに対応します。

こちらは大月市消防本部のはしご車。現在はすでに更新されていますが、このように古いタイプの車両も居たりします。昔のタイプの車両はバケットが脱着式だったため、使用する際に取り付けて使用していました。

こちらは都留市消防本部のはしご車。1978年導入のはしご車で今もまだ現役です。

三菱のグレートをベースとしたはしご車。南アルプス市消防本部のはしご車で、今のはしご車同様にバケットを搭載した状態での収納ができます。

こちらは磐田市消防本部のはしご車。2013年度で更新されてしまいますが、バケット後付タイプの30m級はしご車です。

こちらは今は無きいすゞ810がベースのはしご車。熱海市消防本部の車両で、35m級のはしご車になります。ホテルが多い熱海市だからこその車両かもしれません。

こちらは新潟市消防局のはしご車。日野プロフィアがベースの車両で、50mの高さまで伸ばせるはしごを搭載しています。
なお、現在国内で最大級のはしご車は地上高54mまで伸ばすことが出来ます。
以上で、はしご車 その1を終わります。その2では、はしご車専用車体を使用した車両やクレーン専用車体を利用した車両を紹介します。では
Posted by エルピープルップルン at 20:01│Comments(0)
│消防