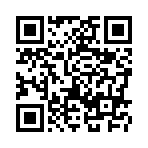2013年08月21日
総務省消防庁車両群
初記事になります。普段は本家「東海の部屋」で記事を書くので、こちらにはあまり書きませんがよろしくお願いします。
では、さっそくですが今回は総務省消防庁からの貸与車両についてまとめてみました。
そもそも、総務省消防庁は簡単に言ってしまえば、日本の消防行政の企画・立案、各種法令・基準の策定をするところで、国の総務省の外局にあたる機関です。つまり、直接的に各自治体の消防本部に対しては助言や補助などしかできず、また火災や災害事案に対して実際に活動を行うわけでもありません。
身近なところで例えれば、トイレの水漏れが起きたからといって市役所の人が直接直しに来るわけではありません。直しに来るのは、その市の認定工事店である水道屋が直接直します。市役所の人は、あくまでその水道屋に対して大まかな規定や方針を助言することしかできません。今回の場合、市役所が総務省消防庁、水道屋が各消防本部になります。
話を戻しますが、総務省消防庁の行っている規格の中で、消防車両の無料貸与制度というものがあります。
消防庁の広報では、「緊急消防援助隊の活動に必要な装備等のうち、地方公共団体による整備が費用対効果の面から非効率的なものについて、この無償使用制度を活用し、各都道府県の代表消防機関等へ全国的に配備しています」と書いてあります。
何を言っているのぞやと思う方が多いと思うので、詳しく説明を加えます。
そもそも、阪神淡路大震災や東日本大震災などが発生した場合、災害地区の消防本部も大きな損害を受けます。例えば阪神淡路大震災の場合では火災、東日本大震災の場合は津波で消防本部が壊滅状態に陥り、消防車両も使えない状況に陥ります。その際に、他県の消防がその災害の救助や消火を行う必要があります。この部隊を緊急援助隊といいます。
もちろん、緊急援助隊というのは各県どの部隊をどれだけ出すかをあらかじめ規定しているためすべての車両が行くわけではありません。つまり静岡県で例えるならば、ポンプ隊は島田市と沼津市、救助隊は浜松市と静岡市、救急隊は富士市と志太広域消防本部(焼津市と藤枝市)というふうに決められています。
次に援助隊に必要な装備などのうち、費用対効果から非効率的なものと言う欄について説明します。
そもそも、消防車両は市の税金から購入されています。その中でも最も使用頻度の高い車両、つまりは怪我や病気などで病院まで搬送する救急車、火災などで出動するポンプ車などは費用対効果から効率的と言えます。
逆に、震災などで使用する重機、夜間の照明などに使用する照明電源車は特殊的な用途にしか使用できず、これは費用対効果から非効率的といえます。
しかし、大災害が起きればこのような非効率車両は重要視されます。重機などは倒壊した建造物破片などを撤去するのに使えますし、照明電源車は夜通しの活動などで明かりを灯し、電気が使用できない場所では電源車としての役割も果たせます。
普段はあまり使用しなくとも、いざというときは必需品となる。この文章はこれを説明しています。しかし、市の予算は毎年限られており、なおかつ1台数千万もする車両を簡単に買うことはできません。
そこで、このような特殊車両を大規模な消防本部(人口が多く予算が小都市に比べて多い場所)や政令指定都市などに国から無償提供することで、大災害発生時に緊急援助隊として活動できるようにというのが、車両貸与制度になります。
普通各消防署には先も書きましたが、救急車やポンプ車、救助工作車や大型水槽車、資機材搬送車や指揮車が置いてありますが、国から貸与車両はこのようなポピュラーな車両ではなく、普段は見ない特殊車両が貸し与えられています。その一部をご紹介します。

特殊災害対策車。NBC(Nuclear、Biological、Chemicalの頭文字。核・生物・化学の意)災害用に制作された車両です。人体に有害な物質が流出または故意に捲かれた場合、それを処理する必要があります。しかし、それが何の物質なのか分からなければ、除去する消防隊にも危険が及びますし、大きな2次災害を起こす可能性があります。その物質を分析するのがこの車両です。中には陽圧室と言うものがあり、外気を中に入れないような構造になっています。政令指定都市などに配備され、静岡県では静岡市消防局千代田消防署、浜松市消防局中消防署鴨江出張所に配備されています。また、NBC災害は最近増加傾向にあるため、各自治体でも自前で入れるようになってきています。

大型除染システム車。上記の特殊災害対策車は、NBC災害の分析を主にしますが、こちらの車両は人体などに付着した汚染物質を除去するための車両です。外観は資機材搬送車ですが、背中のコンテナには大型除染システムのテントなどが入っています。原理としては、テント内に脱衣室・洗浄レーン(歩行可能者レーン2つと歩行不可能者レーン1つ)、着衣室の3つに分かれており、流水による汚染物質の除去をこの中で行います。なお、脱衣・洗浄・着衣の行為を1つとして1時間に200人以上の対応ができるようになっています。静岡県では特殊災害対策車と同じ都市で同じ場所に配備されています。なお、東京消防庁ではテントではなく車両内に除去システムを搭載したものがあります。

特別高度救助車。トラック荷台には大型の扇風機のようなブロアーとウォーターカッターと言う資機材を搭載する小型コンテナが積んであります。ブロアーに関しては、送風だけでなく噴霧放水も可能です。火災時の排煙能力のだけでなく、気体状の危険物質(ガスなど)の排除のほか、フラッシュオーバー防止のための冷却送風の役割を兼ねています。ウォーターカッターは、エンジンカッターなど火花による切断が危険な状況下において、高圧の水を切断物質に充てることでドアなどの切断が行なえます。東京消防庁や大阪府消防局などには、ブロアー車とウォーターカッター車と言う風に別々に配備されていましたが、その後1台の車両に集約されこの車両に至ります。静岡県では、静岡市消防局清水消防署と浜松市消防局東消防署上石田出張所にそれぞれ配備されています。

なお、初期の車両は三菱ファイターがベース車両、現在の車両は上記のいすゞフォワードがベースとなっています。

支援車(1型)です。大災害時に、現場での長期活動を予測し、隊員の衣食住となる部屋の代わりになる車両です。もちろん、物資の搬送も可能で、カートに入れた資機材を運搬することもできます。荷台はドア部が左右に広がるようになっており、キッチン・浴室・洗面などが中に搭載されています。1次車は全国47都道府県に各1台ずつ配備され、静岡県では浜松市消防局北消防署曳馬野出張所に、山梨県では峡北広域行政組合消防本部韮崎消防署に配備されています。なお、総務省消防庁が必要とみなした都市に関しては、2次車が増車され配備されました。

送水車。別名「海水利用型水利システム車」とも言われるこの車両は、2km先まで最大4000L/minの水を送ることのできる車両です。震災などで消火栓が破壊された場合、消火用の水利を確保できません。そのため、この車両が海などの無限水利に隣接し、ポンプをおろして送水します。静岡県では浜松市消防局中消防署に配備されました。

ホース延長車。上記の送水車と2台1組で活動する車両です。荷台には、150mmのホースが2000m搭載されており、送水車が送る水をこの車両の搭載するホースを延長経由させます。静岡県では送水車同様浜松市消防局中消防署に配備されました。

都道府県指揮隊車。緊急援助隊には各都道府県分に出動しますが、その県ごとの隊を指揮する指揮隊も出動します。これは所轄署の指揮隊とは別に、緊急援助隊用の指揮隊(兼任しているところもあるが)として運行されます。静岡や山梨は千用の車両を持っていたのですが、もちろん所轄指揮車を利用しているところもあります。そのため、国で規格化した車両を貸与するに至りました。全国47都道府県に各1台が配備され、静岡県では静岡市消防局石田消防署に、山梨県では甲府広域行政事務組合消防本部南消防署に配備されました。

燃料補給車。災害時、長時間の車両活動により、消防車両などの燃料欠乏を防止するために作成されました。全国配備とはいきませんが、大規模都市や政令指定都市を中心に30台配備されました。静岡県では静岡市消防局追手町消防署平和出張所に配備されました。ちなみに、東京消防庁と横浜市消防局は自前でこの車両を購入しています。

資機材搬送車。先の人員輸送車とほぼセットで導入された車両です。車高が高いのは、悪路でも物資を運べるようにとのことで高床型となりました。リアにはパワーゲートもついており、重い荷物でも積み下ろしができます、全国で46台が配備され、静岡県では御殿場・小山広域消防組合消防本部御殿場消防署に山梨県では大月市消防本部大月消防署に配備されました。

重機運搬車。建造物の倒壊による道路障害や、重量物の撤去などに必要なショベルカーを運ぶ車両です。3型と5型の2種類があり、5型の方がショベルカーの大きさは大きいです。他、ショベルカーには放水銃もついており、ホースをつないで供給すれば放水することもできます。静岡県では、静岡市消防局清水消防署に配備されました。

こちらが、ショベルカーになります。もちろん、アームのアタッチメントも数種類搭載されています。

大規模災害用救助車。大規模災害時に、通常の震災対応の救助工作車と同様の働きをします。なお、車両はⅣ型の救助工作車に準じていますが、装備品は大きく異なり電気式救助機器を装備したERと空気圧式救助機器を搭載したARの2台一組で活動を行います。写真はERタイプ。

こちらはARタイプ。全国に3セットが配備され、うち1セットは静岡県浜松市消防局北消防署に配備されました。
他にも、無線中継車がありますがこちらは静岡県にも山梨県にも配備されなかったため、割愛させてもらいます。
このように特殊災害用の車両が国から無償で提供されることは喜ばしいことですが、配備先の消防本部は部隊用の人員を割かなければならない、緊急援助隊出動時には必ず出動しなければならないなど、負担が大きくなる側面も持っています。
人が少ない消防本部では、提供を断らなければならない事態になる可能性もあります。
無償提供の良し悪しも含めて、今後の消防の課題の一つになっていくと考えられます。
長文になりましたが、初更新はこれで終わります。ここまでお読みいただき、ありがとうございました~
では、さっそくですが今回は総務省消防庁からの貸与車両についてまとめてみました。
そもそも、総務省消防庁は簡単に言ってしまえば、日本の消防行政の企画・立案、各種法令・基準の策定をするところで、国の総務省の外局にあたる機関です。つまり、直接的に各自治体の消防本部に対しては助言や補助などしかできず、また火災や災害事案に対して実際に活動を行うわけでもありません。
身近なところで例えれば、トイレの水漏れが起きたからといって市役所の人が直接直しに来るわけではありません。直しに来るのは、その市の認定工事店である水道屋が直接直します。市役所の人は、あくまでその水道屋に対して大まかな規定や方針を助言することしかできません。今回の場合、市役所が総務省消防庁、水道屋が各消防本部になります。
話を戻しますが、総務省消防庁の行っている規格の中で、消防車両の無料貸与制度というものがあります。
消防庁の広報では、「緊急消防援助隊の活動に必要な装備等のうち、地方公共団体による整備が費用対効果の面から非効率的なものについて、この無償使用制度を活用し、各都道府県の代表消防機関等へ全国的に配備しています」と書いてあります。
何を言っているのぞやと思う方が多いと思うので、詳しく説明を加えます。
そもそも、阪神淡路大震災や東日本大震災などが発生した場合、災害地区の消防本部も大きな損害を受けます。例えば阪神淡路大震災の場合では火災、東日本大震災の場合は津波で消防本部が壊滅状態に陥り、消防車両も使えない状況に陥ります。その際に、他県の消防がその災害の救助や消火を行う必要があります。この部隊を緊急援助隊といいます。
もちろん、緊急援助隊というのは各県どの部隊をどれだけ出すかをあらかじめ規定しているためすべての車両が行くわけではありません。つまり静岡県で例えるならば、ポンプ隊は島田市と沼津市、救助隊は浜松市と静岡市、救急隊は富士市と志太広域消防本部(焼津市と藤枝市)というふうに決められています。
次に援助隊に必要な装備などのうち、費用対効果から非効率的なものと言う欄について説明します。
そもそも、消防車両は市の税金から購入されています。その中でも最も使用頻度の高い車両、つまりは怪我や病気などで病院まで搬送する救急車、火災などで出動するポンプ車などは費用対効果から効率的と言えます。
逆に、震災などで使用する重機、夜間の照明などに使用する照明電源車は特殊的な用途にしか使用できず、これは費用対効果から非効率的といえます。
しかし、大災害が起きればこのような非効率車両は重要視されます。重機などは倒壊した建造物破片などを撤去するのに使えますし、照明電源車は夜通しの活動などで明かりを灯し、電気が使用できない場所では電源車としての役割も果たせます。
普段はあまり使用しなくとも、いざというときは必需品となる。この文章はこれを説明しています。しかし、市の予算は毎年限られており、なおかつ1台数千万もする車両を簡単に買うことはできません。
そこで、このような特殊車両を大規模な消防本部(人口が多く予算が小都市に比べて多い場所)や政令指定都市などに国から無償提供することで、大災害発生時に緊急援助隊として活動できるようにというのが、車両貸与制度になります。
普通各消防署には先も書きましたが、救急車やポンプ車、救助工作車や大型水槽車、資機材搬送車や指揮車が置いてありますが、国から貸与車両はこのようなポピュラーな車両ではなく、普段は見ない特殊車両が貸し与えられています。その一部をご紹介します。

特殊災害対策車。NBC(Nuclear、Biological、Chemicalの頭文字。核・生物・化学の意)災害用に制作された車両です。人体に有害な物質が流出または故意に捲かれた場合、それを処理する必要があります。しかし、それが何の物質なのか分からなければ、除去する消防隊にも危険が及びますし、大きな2次災害を起こす可能性があります。その物質を分析するのがこの車両です。中には陽圧室と言うものがあり、外気を中に入れないような構造になっています。政令指定都市などに配備され、静岡県では静岡市消防局千代田消防署、浜松市消防局中消防署鴨江出張所に配備されています。また、NBC災害は最近増加傾向にあるため、各自治体でも自前で入れるようになってきています。

大型除染システム車。上記の特殊災害対策車は、NBC災害の分析を主にしますが、こちらの車両は人体などに付着した汚染物質を除去するための車両です。外観は資機材搬送車ですが、背中のコンテナには大型除染システムのテントなどが入っています。原理としては、テント内に脱衣室・洗浄レーン(歩行可能者レーン2つと歩行不可能者レーン1つ)、着衣室の3つに分かれており、流水による汚染物質の除去をこの中で行います。なお、脱衣・洗浄・着衣の行為を1つとして1時間に200人以上の対応ができるようになっています。静岡県では特殊災害対策車と同じ都市で同じ場所に配備されています。なお、東京消防庁ではテントではなく車両内に除去システムを搭載したものがあります。

特別高度救助車。トラック荷台には大型の扇風機のようなブロアーとウォーターカッターと言う資機材を搭載する小型コンテナが積んであります。ブロアーに関しては、送風だけでなく噴霧放水も可能です。火災時の排煙能力のだけでなく、気体状の危険物質(ガスなど)の排除のほか、フラッシュオーバー防止のための冷却送風の役割を兼ねています。ウォーターカッターは、エンジンカッターなど火花による切断が危険な状況下において、高圧の水を切断物質に充てることでドアなどの切断が行なえます。東京消防庁や大阪府消防局などには、ブロアー車とウォーターカッター車と言う風に別々に配備されていましたが、その後1台の車両に集約されこの車両に至ります。静岡県では、静岡市消防局清水消防署と浜松市消防局東消防署上石田出張所にそれぞれ配備されています。

なお、初期の車両は三菱ファイターがベース車両、現在の車両は上記のいすゞフォワードがベースとなっています。

支援車(1型)です。大災害時に、現場での長期活動を予測し、隊員の衣食住となる部屋の代わりになる車両です。もちろん、物資の搬送も可能で、カートに入れた資機材を運搬することもできます。荷台はドア部が左右に広がるようになっており、キッチン・浴室・洗面などが中に搭載されています。1次車は全国47都道府県に各1台ずつ配備され、静岡県では浜松市消防局北消防署曳馬野出張所に、山梨県では峡北広域行政組合消防本部韮崎消防署に配備されています。なお、総務省消防庁が必要とみなした都市に関しては、2次車が増車され配備されました。

送水車。別名「海水利用型水利システム車」とも言われるこの車両は、2km先まで最大4000L/minの水を送ることのできる車両です。震災などで消火栓が破壊された場合、消火用の水利を確保できません。そのため、この車両が海などの無限水利に隣接し、ポンプをおろして送水します。静岡県では浜松市消防局中消防署に配備されました。

ホース延長車。上記の送水車と2台1組で活動する車両です。荷台には、150mmのホースが2000m搭載されており、送水車が送る水をこの車両の搭載するホースを延長経由させます。静岡県では送水車同様浜松市消防局中消防署に配備されました。

都道府県指揮隊車。緊急援助隊には各都道府県分に出動しますが、その県ごとの隊を指揮する指揮隊も出動します。これは所轄署の指揮隊とは別に、緊急援助隊用の指揮隊(兼任しているところもあるが)として運行されます。静岡や山梨は千用の車両を持っていたのですが、もちろん所轄指揮車を利用しているところもあります。そのため、国で規格化した車両を貸与するに至りました。全国47都道府県に各1台が配備され、静岡県では静岡市消防局石田消防署に、山梨県では甲府広域行政事務組合消防本部南消防署に配備されました。

燃料補給車。災害時、長時間の車両活動により、消防車両などの燃料欠乏を防止するために作成されました。全国配備とはいきませんが、大規模都市や政令指定都市を中心に30台配備されました。静岡県では静岡市消防局追手町消防署平和出張所に配備されました。ちなみに、東京消防庁と横浜市消防局は自前でこの車両を購入しています。

資機材搬送車。先の人員輸送車とほぼセットで導入された車両です。車高が高いのは、悪路でも物資を運べるようにとのことで高床型となりました。リアにはパワーゲートもついており、重い荷物でも積み下ろしができます、全国で46台が配備され、静岡県では御殿場・小山広域消防組合消防本部御殿場消防署に山梨県では大月市消防本部大月消防署に配備されました。

重機運搬車。建造物の倒壊による道路障害や、重量物の撤去などに必要なショベルカーを運ぶ車両です。3型と5型の2種類があり、5型の方がショベルカーの大きさは大きいです。他、ショベルカーには放水銃もついており、ホースをつないで供給すれば放水することもできます。静岡県では、静岡市消防局清水消防署に配備されました。

こちらが、ショベルカーになります。もちろん、アームのアタッチメントも数種類搭載されています。

大規模災害用救助車。大規模災害時に、通常の震災対応の救助工作車と同様の働きをします。なお、車両はⅣ型の救助工作車に準じていますが、装備品は大きく異なり電気式救助機器を装備したERと空気圧式救助機器を搭載したARの2台一組で活動を行います。写真はERタイプ。

こちらはARタイプ。全国に3セットが配備され、うち1セットは静岡県浜松市消防局北消防署に配備されました。
他にも、無線中継車がありますがこちらは静岡県にも山梨県にも配備されなかったため、割愛させてもらいます。
このように特殊災害用の車両が国から無償で提供されることは喜ばしいことですが、配備先の消防本部は部隊用の人員を割かなければならない、緊急援助隊出動時には必ず出動しなければならないなど、負担が大きくなる側面も持っています。
人が少ない消防本部では、提供を断らなければならない事態になる可能性もあります。
無償提供の良し悪しも含めて、今後の消防の課題の一つになっていくと考えられます。
長文になりましたが、初更新はこれで終わります。ここまでお読みいただき、ありがとうございました~
Posted by エルピープルップルン at 19:40│Comments(0)
│消防