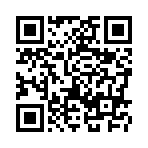2013年09月11日
救助工作車
こんにちは。今回は前回予告していた通り、救助工作車のことについて説明したいと思います。
救助工作車とは、火を消すポンプ車とは違い人命救助のための車両になります。けが人を処置して病院に搬送するのは救急隊ですが、そのけが人が自力で脱出できない場合は救助隊が救うことになります。
その救うための機材を搭載し出動するのが救助工作車なのです。一般的に救助隊はオレンジの服を着て、他の部隊とは違う雰囲気を出しています。また、消防で一番憧れが多いのはやはり救助隊で、人気も一番あります。
さて救助工作車ですが、ポンプ車と同様にⅠ型~Ⅳ型までタイプがあります。
まずはⅠ型ですが、こちらは2~3tベースの小型トラックを用いた車両です。人口の少ない小規模自治体では使われていた車両ですが、近年はⅡ型もしくはポンプ車兼用車両としての導入が多く、Ⅰ型の救助工作車はほとんどありません。
次にⅡ型です。Ⅱ型は5t~7tベースのトラックを用いた車両で、今一番普及している車両です。Ⅱ型は一般災害及び救助事案に対応する資機材を搭載しており、後部にクレーンを搭載している車両もいます。

救助工作車Ⅱ型(写真は富士宮市消防本部中央消防署の車両)。前面にはウインチも搭載しており、後部にはクレーンも搭載しています。

こちらも救助工作車Ⅱ型(写真は甲府広域行政事務組合消防本部西消防署の車両)。こちらは平成2年に導入された車両で、総排気量が12000ccクラスなのでいすゞ810がベースの車両と思われる。車両的には8tクラスがベースと思われ、静岡県内にはこのサイズのⅡ型救助工作車はありません。
次にⅢ型です。Ⅲ型は震災対応の救助工作車で、Ⅱ型の救助資機材にくわえ高度救助資機材(二酸化炭素探査装置、画像探索機など)を搭載している車両が該当します。車体は7t~10tベースのトラック(震災対応のため、悪路走行を考慮し高床型を採用しているところが多い)を利用し、クレーンは標準装備しています。なお、車体がⅢ型に準じていても、クレーンを装備していなかったり、高度救助資機材を搭載していない場合はⅡ型に分類されます。

Ⅲ型の救助工作車(写真は富士市消防本部中央消防署の車両)。悪路の走行も考慮し、車高が高くなっています。

こちらは新潟市消防局中央消防署の車両。上記のⅢ型救助工作車と同様、車高の高い車両を使用していますが、こちらのベースは除雪車のトラックをベースにしています。

こちらは浜松市消防局中消防署鴨江出張所の救助工作車。車両は高床ではなく低床タイプですが、デッキ部分にFSV(FireSkyView)を採用しており、資機材の搭載及び上部視野の確保ができました。
最後にⅣ型。阪神大震災以降、震災対応車両としてⅢ型同様に開発された車両ですが、Ⅲ型と違うのは空路輸送も考慮されている点です。資機材はⅢ型に準じたものになっていますが、自衛隊のC-130輸送機には積むことができません。そのため、C-130に積めるようにするため、Ⅲ型の搭載資機材を2台の小型トラックに分散しました。これがⅣ型です。
Ⅳ型は2台一組のため、維持費などの関係やC-130での輸送が大震災などの災害時のみ(阪神大震災以降、震災時にC-130で輸送したケースは今のところない)のため、導入している自治体はそう多くありません。

Ⅳ型救助工作車(写真は浜松市消防局天竜消防署の車両)

Ⅳ型救助工作車(写真は浜松市消防局天竜消防署の車両)
この2台一組で行動します。なお、浜松市はⅣ型の救助工作車の片方にポンプ機能を搭載しており、火災にも対応しています。また、全国でⅣ型の救助工作車を導入しているのは、東京消防庁・名古屋市消防局、大阪府消防局、福岡市消防局、浜松市消防局、さいたま市消防局の6都市しかありません(2012年度に貸与された大規模震災用高度救助車はⅣ型ベースの車両と判断し除く)
以上、Ⅰ型~Ⅳ型の説明でした。では、少しだけ派生形を見てみましょう。

こちらは新潟市消防局西消防署小針出張所の車両。コードは小針Rですが、ポンプを搭載しているため主に火災対応で運用していると思われます。

こちらは田方消防本部南消防署の救助工作車。コードは田方45(撮影当時は42)で、ポンプ及び水槽も搭載しているようです。

こちらは島田市消防本部金谷消防署の救助工作車。こちらも水槽(950L)を搭載しており、交通事故・火災に対応しています。なお、某氏からの情報によると、破損によりこの車両はすでに廃車になっているとか。

こちらはすでに廃車になった島田市消防本部金谷消防署の救助工作車。車体は古いですが、Ⅱ型救助工作車に該当すると思われます。
以上で救助工作車の説明を終わります。次回は、赤い車両が並ぶ中で唯一白い色を纏い、一番出動件数が多い救急車について特集します。では
救助工作車とは、火を消すポンプ車とは違い人命救助のための車両になります。けが人を処置して病院に搬送するのは救急隊ですが、そのけが人が自力で脱出できない場合は救助隊が救うことになります。
その救うための機材を搭載し出動するのが救助工作車なのです。一般的に救助隊はオレンジの服を着て、他の部隊とは違う雰囲気を出しています。また、消防で一番憧れが多いのはやはり救助隊で、人気も一番あります。
さて救助工作車ですが、ポンプ車と同様にⅠ型~Ⅳ型までタイプがあります。
まずはⅠ型ですが、こちらは2~3tベースの小型トラックを用いた車両です。人口の少ない小規模自治体では使われていた車両ですが、近年はⅡ型もしくはポンプ車兼用車両としての導入が多く、Ⅰ型の救助工作車はほとんどありません。
次にⅡ型です。Ⅱ型は5t~7tベースのトラックを用いた車両で、今一番普及している車両です。Ⅱ型は一般災害及び救助事案に対応する資機材を搭載しており、後部にクレーンを搭載している車両もいます。

救助工作車Ⅱ型(写真は富士宮市消防本部中央消防署の車両)。前面にはウインチも搭載しており、後部にはクレーンも搭載しています。

こちらも救助工作車Ⅱ型(写真は甲府広域行政事務組合消防本部西消防署の車両)。こちらは平成2年に導入された車両で、総排気量が12000ccクラスなのでいすゞ810がベースの車両と思われる。車両的には8tクラスがベースと思われ、静岡県内にはこのサイズのⅡ型救助工作車はありません。
次にⅢ型です。Ⅲ型は震災対応の救助工作車で、Ⅱ型の救助資機材にくわえ高度救助資機材(二酸化炭素探査装置、画像探索機など)を搭載している車両が該当します。車体は7t~10tベースのトラック(震災対応のため、悪路走行を考慮し高床型を採用しているところが多い)を利用し、クレーンは標準装備しています。なお、車体がⅢ型に準じていても、クレーンを装備していなかったり、高度救助資機材を搭載していない場合はⅡ型に分類されます。

Ⅲ型の救助工作車(写真は富士市消防本部中央消防署の車両)。悪路の走行も考慮し、車高が高くなっています。

こちらは新潟市消防局中央消防署の車両。上記のⅢ型救助工作車と同様、車高の高い車両を使用していますが、こちらのベースは除雪車のトラックをベースにしています。

こちらは浜松市消防局中消防署鴨江出張所の救助工作車。車両は高床ではなく低床タイプですが、デッキ部分にFSV(FireSkyView)を採用しており、資機材の搭載及び上部視野の確保ができました。
最後にⅣ型。阪神大震災以降、震災対応車両としてⅢ型同様に開発された車両ですが、Ⅲ型と違うのは空路輸送も考慮されている点です。資機材はⅢ型に準じたものになっていますが、自衛隊のC-130輸送機には積むことができません。そのため、C-130に積めるようにするため、Ⅲ型の搭載資機材を2台の小型トラックに分散しました。これがⅣ型です。
Ⅳ型は2台一組のため、維持費などの関係やC-130での輸送が大震災などの災害時のみ(阪神大震災以降、震災時にC-130で輸送したケースは今のところない)のため、導入している自治体はそう多くありません。

Ⅳ型救助工作車(写真は浜松市消防局天竜消防署の車両)

Ⅳ型救助工作車(写真は浜松市消防局天竜消防署の車両)
この2台一組で行動します。なお、浜松市はⅣ型の救助工作車の片方にポンプ機能を搭載しており、火災にも対応しています。また、全国でⅣ型の救助工作車を導入しているのは、東京消防庁・名古屋市消防局、大阪府消防局、福岡市消防局、浜松市消防局、さいたま市消防局の6都市しかありません(2012年度に貸与された大規模震災用高度救助車はⅣ型ベースの車両と判断し除く)
以上、Ⅰ型~Ⅳ型の説明でした。では、少しだけ派生形を見てみましょう。

こちらは新潟市消防局西消防署小針出張所の車両。コードは小針Rですが、ポンプを搭載しているため主に火災対応で運用していると思われます。

こちらは田方消防本部南消防署の救助工作車。コードは田方45(撮影当時は42)で、ポンプ及び水槽も搭載しているようです。

こちらは島田市消防本部金谷消防署の救助工作車。こちらも水槽(950L)を搭載しており、交通事故・火災に対応しています。なお、某氏からの情報によると、破損によりこの車両はすでに廃車になっているとか。

こちらはすでに廃車になった島田市消防本部金谷消防署の救助工作車。車体は古いですが、Ⅱ型救助工作車に該当すると思われます。
以上で救助工作車の説明を終わります。次回は、赤い車両が並ぶ中で唯一白い色を纏い、一番出動件数が多い救急車について特集します。では
Posted by エルピープルップルン at 22:54│Comments(0)
│消防