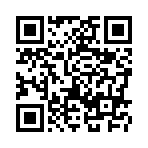2014年05月12日
はしご車 その2
こんにちは。今回は前回に引き続き、はしご車の特集です。前回では、一般のトラックをベースにしたはしご車を紹介しましたが、今回ははしご車専用車体及びクレーン車専用車体がベースのはしご車を紹介します。
現在、日本で使用されているはしご車の大半が、モリタ製のはしご車で、MHシリーズというものがあります。
これは、はしご車専用車体を使用したもので、現在のモデルはMH-2になります。

こちらは最初に登場したMHシリーズ。MH-1という車体を利用した車両で、多くの消防本部に配備されました。写真は静岡市消防局の車両。

こちらがMH-2。MH-2MAXと普通のMH-2がありますが細かい部分で違いがあります。何が違うか忘れてしまいましたが・・・
お次はクレーン車ベースの車体。4WS機能を搭載し、クレーンを搭載していた車体ははしご車用でも使えるだろうとして造られました。

こちらがそれ。トミカでも昔販売されていました。AZ-30型と呼ばれるもので、クレーン車体ベースのはしご車です。4WS機能を搭載し最小半径5m以内という高い旋回能力を持ち、斜め平行移動も可能でした。しかし、エンジンが非力な上3ATで最高速度が50km出ないという欠点を持ち、減速からの再加速が苦手だったため、運動性能的にはかなりきついものだったようです。写真は静岡市消防局の車両で、現在は更新されありません。

こちらは甲府広域行政組合消防本部の車両。バンパーがメッキ仕様になっています。こちらもすでに更新済。

こちらは志太広域消防本部のはしご車。静岡県内では唯一生き残っているAZ-30型です。

さらにこちらは諏訪広域行政組合消防本部の車両。タダノのクレーン車体ではなく日産ディーゼル(現UDトラックス)のレゾナのキャブを用いた車体です。このタイプも昔はそこそこ配備されていましたが、今では風前の灯火です。
そして今回最後は外国製のはしご車を。
日本で使用されている外国製のはしご車は、現在マギルスというメーカーのもののみとなります(ベンツのはしご車もありますが、現在新製されて配備されることがないため省きました)

こちらがその車両。車体にはイベコとありますが、元々イベコはイタリアのメーカーでイベコ・マギルスはドイツのメーカーになります(消防車専門として分社化した?)
日本では国内に50m級のはしご車を作れる会社がなかったため、近鉄モータース(現在のモリタテクノス)が輸入を始めたところが起点と言われています。写真は東山梨事務行政組合消防本部の車両で、平成2年に導入されました。東京消防庁でもこのタイプの車両は多く導入されましたが、排ガス規制などの関係で現在はイベコの車体を使わず国産のものを利用しています。

こちらがマギルスのはしごを搭載した国産車体のはしご車。車体は日野プロフィアの車体を利用し、はしごのみマギルス製のものを利用しています。マギルスのはしごはマイナス仰角や先端屈折などの特許を多く持っており、現在でも利便性に優れるなどで各消防本部に導入されています。写真は小田原市消防本部の車両。

こちらは東京消防庁の車両。東京消防庁に導入されているマギルスのはしご車はすべて40m級なんだそうです。
以上でその2を終わります。その3では屈折放水車やシュノーケル車を紹介します。では
現在、日本で使用されているはしご車の大半が、モリタ製のはしご車で、MHシリーズというものがあります。
これは、はしご車専用車体を使用したもので、現在のモデルはMH-2になります。

こちらは最初に登場したMHシリーズ。MH-1という車体を利用した車両で、多くの消防本部に配備されました。写真は静岡市消防局の車両。

こちらがMH-2。MH-2MAXと普通のMH-2がありますが細かい部分で違いがあります。何が違うか忘れてしまいましたが・・・
お次はクレーン車ベースの車体。4WS機能を搭載し、クレーンを搭載していた車体ははしご車用でも使えるだろうとして造られました。

こちらがそれ。トミカでも昔販売されていました。AZ-30型と呼ばれるもので、クレーン車体ベースのはしご車です。4WS機能を搭載し最小半径5m以内という高い旋回能力を持ち、斜め平行移動も可能でした。しかし、エンジンが非力な上3ATで最高速度が50km出ないという欠点を持ち、減速からの再加速が苦手だったため、運動性能的にはかなりきついものだったようです。写真は静岡市消防局の車両で、現在は更新されありません。

こちらは甲府広域行政組合消防本部の車両。バンパーがメッキ仕様になっています。こちらもすでに更新済。

こちらは志太広域消防本部のはしご車。静岡県内では唯一生き残っているAZ-30型です。

さらにこちらは諏訪広域行政組合消防本部の車両。タダノのクレーン車体ではなく日産ディーゼル(現UDトラックス)のレゾナのキャブを用いた車体です。このタイプも昔はそこそこ配備されていましたが、今では風前の灯火です。
そして今回最後は外国製のはしご車を。
日本で使用されている外国製のはしご車は、現在マギルスというメーカーのもののみとなります(ベンツのはしご車もありますが、現在新製されて配備されることがないため省きました)

こちらがその車両。車体にはイベコとありますが、元々イベコはイタリアのメーカーでイベコ・マギルスはドイツのメーカーになります(消防車専門として分社化した?)
日本では国内に50m級のはしご車を作れる会社がなかったため、近鉄モータース(現在のモリタテクノス)が輸入を始めたところが起点と言われています。写真は東山梨事務行政組合消防本部の車両で、平成2年に導入されました。東京消防庁でもこのタイプの車両は多く導入されましたが、排ガス規制などの関係で現在はイベコの車体を使わず国産のものを利用しています。

こちらがマギルスのはしごを搭載した国産車体のはしご車。車体は日野プロフィアの車体を利用し、はしごのみマギルス製のものを利用しています。マギルスのはしごはマイナス仰角や先端屈折などの特許を多く持っており、現在でも利便性に優れるなどで各消防本部に導入されています。写真は小田原市消防本部の車両。

こちらは東京消防庁の車両。東京消防庁に導入されているマギルスのはしご車はすべて40m級なんだそうです。
以上でその2を終わります。その3では屈折放水車やシュノーケル車を紹介します。では
2014年01月30日
はしご車 その1
お久しぶりです。今回は予告通り「はしご車」の特集です。なお、写真の関係上今回はその1とさせていただきます。
はしご車とはご存じの通り、高層階での災害に対応する車両です。主にビル火災などの消火・救助を任とし、山岳救助や水難救助で使用している自治体もあります。また、屈折放水車や屈折はしご車などもはしご車の分類に含まれます。
はしごの長さもそれぞれで、短いものは15m級、長いものは50m級と幅は広いです。また、使用頻度も低いためベースとなっている車両も一世代や二世代前の車両が使われている自治体が多いです。なお今のはしご車はほとんどがはしご車専用車体を使用しており、ほとんど自治体が同じタイプのはしご車を使用しています。

こちらは浜松市消防局のはしご車。15m級の小型はしご車で、3階などの建物火災などに対応します。

こちらは大月市消防本部のはしご車。現在はすでに更新されていますが、このように古いタイプの車両も居たりします。昔のタイプの車両はバケットが脱着式だったため、使用する際に取り付けて使用していました。

こちらは都留市消防本部のはしご車。1978年導入のはしご車で今もまだ現役です。

三菱のグレートをベースとしたはしご車。南アルプス市消防本部のはしご車で、今のはしご車同様にバケットを搭載した状態での収納ができます。

こちらは磐田市消防本部のはしご車。2013年度で更新されてしまいますが、バケット後付タイプの30m級はしご車です。

こちらは今は無きいすゞ810がベースのはしご車。熱海市消防本部の車両で、35m級のはしご車になります。ホテルが多い熱海市だからこその車両かもしれません。

こちらは新潟市消防局のはしご車。日野プロフィアがベースの車両で、50mの高さまで伸ばせるはしごを搭載しています。
なお、現在国内で最大級のはしご車は地上高54mまで伸ばすことが出来ます。
以上で、はしご車 その1を終わります。その2では、はしご車専用車体を使用した車両やクレーン専用車体を利用した車両を紹介します。では
はしご車とはご存じの通り、高層階での災害に対応する車両です。主にビル火災などの消火・救助を任とし、山岳救助や水難救助で使用している自治体もあります。また、屈折放水車や屈折はしご車などもはしご車の分類に含まれます。
はしごの長さもそれぞれで、短いものは15m級、長いものは50m級と幅は広いです。また、使用頻度も低いためベースとなっている車両も一世代や二世代前の車両が使われている自治体が多いです。なお今のはしご車はほとんどがはしご車専用車体を使用しており、ほとんど自治体が同じタイプのはしご車を使用しています。

こちらは浜松市消防局のはしご車。15m級の小型はしご車で、3階などの建物火災などに対応します。

こちらは大月市消防本部のはしご車。現在はすでに更新されていますが、このように古いタイプの車両も居たりします。昔のタイプの車両はバケットが脱着式だったため、使用する際に取り付けて使用していました。

こちらは都留市消防本部のはしご車。1978年導入のはしご車で今もまだ現役です。

三菱のグレートをベースとしたはしご車。南アルプス市消防本部のはしご車で、今のはしご車同様にバケットを搭載した状態での収納ができます。

こちらは磐田市消防本部のはしご車。2013年度で更新されてしまいますが、バケット後付タイプの30m級はしご車です。

こちらは今は無きいすゞ810がベースのはしご車。熱海市消防本部の車両で、35m級のはしご車になります。ホテルが多い熱海市だからこその車両かもしれません。

こちらは新潟市消防局のはしご車。日野プロフィアがベースの車両で、50mの高さまで伸ばせるはしごを搭載しています。
なお、現在国内で最大級のはしご車は地上高54mまで伸ばすことが出来ます。
以上で、はしご車 その1を終わります。その2では、はしご車専用車体を使用した車両やクレーン専用車体を利用した車両を紹介します。では
2013年12月25日
化学車
こんにちは。今回は予告していた通り、化学消防車(以下化学車)を特集します。
化学車とは、ポンプ車に薬液を積み、水と混合して消火する車両です。
油火災などは、水をかけると逆に火の勢いが強くなってしまうため、粉末消火材や泡消火材を混合します。そのため、石油化学工場やコンビナートが点在する都市の消防本部や、その自衛消防隊には化学車が配備されています。
化学車にも水槽容量などや車両サイズにより型式を分けることができ、Ⅰ型~Ⅴ型と大Ⅰ、大Ⅱ型の7種類に分けることができます。一般的な消防本部ではⅠ型とⅡ型が配備され、工場や化学工場が点在する消防本部ではⅢ型~Ⅴ型が配備されています。また港などのコンビナートを抱える消防本部では化学車3点セットとして大Ⅰ型が配備され、空港の航空局などが所有するのが大Ⅱ型です。
では、それぞれの形式を見ていきましょう。

こちらがⅠ型の化学車。1000Lの水槽と315Lの薬液槽を搭載しています。車両火災や小規模化学火災などで使用され、タンク車として使用している消防本部も少なくありません。なお、写真は富士宮市消防本部の車両。

こちらはⅡ型の化学車。1500Lの水槽と500Lの薬液槽を搭載しています。一般火災にも対応することができるため、Ⅰ型に比べて幅広い火災に対応することができます。写真は田方消防本部の車両。

こちらはⅢ型。7t~8tベースの車両を使用し、1300Lの水槽と1200Lの薬液槽を搭載しており、工場火災にも対応することができます。写真は富士市消防本部の車両。

こちらは浜松市消防本部の車両。Ⅲ型タイプの車両ですが、配備年数が平成12年のため、荷台がオールシャッタータイプではなく、露出タイプになっています。

こちらはⅣ型。8tベースの車両を使用し、2000Lの水槽と1600Lの薬液槽を搭載しています。また化学車特有の放水銃を2門装備しているのが特徴です。Ⅲ型並びにⅤ型の化学車の化学車の中間のためか、配備している消防本部は少ないです。
Ⅴ型は該当車両が私の撮影した車両の中にいなかったため、代わりの車両を。

こちらは更新された静岡市消防局の車両。区分は大Ⅰ型ですが、水槽2000L薬液1800Lを搭載していますので、Ⅴ型に近いものとなっています(ただし、車体は2軸車なのでⅤ型で定義している3軸車とは異なる)

こちらは大Ⅰ型。基本的にはⅤ型と同じですが、高所放水車並びに泡原液搬送車と3点でチームを組みコンビナート火災に対応します。なお写真は上記の更新後の車両で、水槽1500L薬液1800Lを搭載しています。水槽容量が少ないのは、コンビナート火災の際は他のポンプ車から送水を主とするためで、水槽自体を搭載してない車両も存在します。

こちらは大Ⅱ型。空港型大型化学車の分類となり、基本的に消防本部に配備されている車両は少なく、航空局が所有している場合が多いです。なお写真は東京国際防災展で撮影した大Ⅱ型。
以上で、化学車の説明を終わります。次回はビルなどの火災で対応するはしご車を特集します。では
化学車とは、ポンプ車に薬液を積み、水と混合して消火する車両です。
油火災などは、水をかけると逆に火の勢いが強くなってしまうため、粉末消火材や泡消火材を混合します。そのため、石油化学工場やコンビナートが点在する都市の消防本部や、その自衛消防隊には化学車が配備されています。
化学車にも水槽容量などや車両サイズにより型式を分けることができ、Ⅰ型~Ⅴ型と大Ⅰ、大Ⅱ型の7種類に分けることができます。一般的な消防本部ではⅠ型とⅡ型が配備され、工場や化学工場が点在する消防本部ではⅢ型~Ⅴ型が配備されています。また港などのコンビナートを抱える消防本部では化学車3点セットとして大Ⅰ型が配備され、空港の航空局などが所有するのが大Ⅱ型です。
では、それぞれの形式を見ていきましょう。

こちらがⅠ型の化学車。1000Lの水槽と315Lの薬液槽を搭載しています。車両火災や小規模化学火災などで使用され、タンク車として使用している消防本部も少なくありません。なお、写真は富士宮市消防本部の車両。

こちらはⅡ型の化学車。1500Lの水槽と500Lの薬液槽を搭載しています。一般火災にも対応することができるため、Ⅰ型に比べて幅広い火災に対応することができます。写真は田方消防本部の車両。

こちらはⅢ型。7t~8tベースの車両を使用し、1300Lの水槽と1200Lの薬液槽を搭載しており、工場火災にも対応することができます。写真は富士市消防本部の車両。

こちらは浜松市消防本部の車両。Ⅲ型タイプの車両ですが、配備年数が平成12年のため、荷台がオールシャッタータイプではなく、露出タイプになっています。

こちらはⅣ型。8tベースの車両を使用し、2000Lの水槽と1600Lの薬液槽を搭載しています。また化学車特有の放水銃を2門装備しているのが特徴です。Ⅲ型並びにⅤ型の化学車の化学車の中間のためか、配備している消防本部は少ないです。
Ⅴ型は該当車両が私の撮影した車両の中にいなかったため、代わりの車両を。

こちらは更新された静岡市消防局の車両。区分は大Ⅰ型ですが、水槽2000L薬液1800Lを搭載していますので、Ⅴ型に近いものとなっています(ただし、車体は2軸車なのでⅤ型で定義している3軸車とは異なる)

こちらは大Ⅰ型。基本的にはⅤ型と同じですが、高所放水車並びに泡原液搬送車と3点でチームを組みコンビナート火災に対応します。なお写真は上記の更新後の車両で、水槽1500L薬液1800Lを搭載しています。水槽容量が少ないのは、コンビナート火災の際は他のポンプ車から送水を主とするためで、水槽自体を搭載してない車両も存在します。
こちらは大Ⅱ型。空港型大型化学車の分類となり、基本的に消防本部に配備されている車両は少なく、航空局が所有している場合が多いです。なお写真は東京国際防災展で撮影した大Ⅱ型。
以上で、化学車の説明を終わります。次回はビルなどの火災で対応するはしご車を特集します。では
2013年11月30日
救急車 その3
こんばんは。今回は救急車 その3です。
その3では、その1及びその2で紹介した、トヨタ並びに日産以外の救急車を紹介します。

札幌ボデーが販売している救急車はトライハートと呼ばれ、1992年に札幌市消防局との共同開発で誕生しました。高床キャンターをベースにすることで悪路の走破にも優れ、またトラックベースから室内空間の広さを実現しました。
1992年以降5代目キャンターから7代目キャンターまでのモデルが使用されていましたが、8代目キャンターが登場する際にエアサスのモデルが消滅するため、2008年からはいすゞエルフエアサス車をベースのものに変わりました。
なお、乗員定数は10名と国内高規格救急車では最大の人数を乗せることができます(なお3代目ハイメディックは8名)
写真は長野県諏訪広域消防本部の車両で7代目キャンターをベースにしています。
ちなみに、国産高規格救急車でトラックベースで販売しているものは、現在このトライハートのみとなっています。

三菱自動車が1997年に登場させた高規格救急車がディアメディックです(写真は島田市消防本部の車両。更新済み)
上記トライハートと同様にキャンターをベースにしていますが、短尺のボディを使用し最少半径4.9mという小回りを実現しました。東京消防庁などでも導入されましたが、2002年にキャンターのフルモデルチェンジに伴い生産終了となりました。

帝国繊維が発売していた救急車はオプティマと呼ばれていました。こちらはディアメディックに比べ車体長が長く、正にトラックベースの救急車というものでした。現在はほとんどが廃車になっており、予備車として残っている車両も少なくなってきています。

いすゞ自動車は、1995年にトラックベースのスーパーメディックを発売していました。こちらはいすゞエルフをベースとした車両で、トライハートやオプティマに比べ横に広い印象の車両でした(写真は三島市消防本部の車両。更新済み)

なお、低床と高床の2車種がありましたが、乗り心地などは悪いようです(写真は富士市消防本部の車両。更新済み)

トラックベースで最大級と言えば、東京消防庁が導入したスーパーアンビュランスが思い浮かびます。
こちらは1台目(すでに更新済み)、2台目ともに三菱ふそうグレート(2台目はスーパーグレート)をベースにしており、傷病者の収容数も高規格救急車などよりはるかに大きいものとなっています。なお、東京消防庁には現在2台が在籍しており、第2方面隊ハイパーレスキューに2台目が、第8方面隊ハイパーレスキューには3台目(いすゞギガベース)が配備されています。
この他にも、マイクロバスをベースとした救急車が存在し、消防本部所属車両では東京消防庁第3方面隊ハイパーレスキューの車両と愛知県知多中部広域事務組合消防本部に配備されています。

こちらは病院のドクターカー。規模の大きい病院では、ドクターカーやNICU(新生児集中治療)としての車両で導入されることが多く、消防ではあまり見られないマイクロバスベースの救急車がいたりします。なお、最近では搬送を救急車にし、初期治療で医師が同行するケースが多くなってきたため、医師と初期治療設備を運ぶためだけのドクターカーが増えてきています。これらの車両はセダンタイプやステーションワゴンの車両またはRV車ベースの車両が多く、小回りが利く点ではマイクロバスなどに比べて優れています。
以上で、その1~その3まで特集しました救急車についての説明を終わります。
次回は、化学工場や規模が大きい油火災などで活躍する化学車を特集します。では
その3では、その1及びその2で紹介した、トヨタ並びに日産以外の救急車を紹介します。

札幌ボデーが販売している救急車はトライハートと呼ばれ、1992年に札幌市消防局との共同開発で誕生しました。高床キャンターをベースにすることで悪路の走破にも優れ、またトラックベースから室内空間の広さを実現しました。
1992年以降5代目キャンターから7代目キャンターまでのモデルが使用されていましたが、8代目キャンターが登場する際にエアサスのモデルが消滅するため、2008年からはいすゞエルフエアサス車をベースのものに変わりました。
なお、乗員定数は10名と国内高規格救急車では最大の人数を乗せることができます(なお3代目ハイメディックは8名)
写真は長野県諏訪広域消防本部の車両で7代目キャンターをベースにしています。
ちなみに、国産高規格救急車でトラックベースで販売しているものは、現在このトライハートのみとなっています。

三菱自動車が1997年に登場させた高規格救急車がディアメディックです(写真は島田市消防本部の車両。更新済み)
上記トライハートと同様にキャンターをベースにしていますが、短尺のボディを使用し最少半径4.9mという小回りを実現しました。東京消防庁などでも導入されましたが、2002年にキャンターのフルモデルチェンジに伴い生産終了となりました。

帝国繊維が発売していた救急車はオプティマと呼ばれていました。こちらはディアメディックに比べ車体長が長く、正にトラックベースの救急車というものでした。現在はほとんどが廃車になっており、予備車として残っている車両も少なくなってきています。

いすゞ自動車は、1995年にトラックベースのスーパーメディックを発売していました。こちらはいすゞエルフをベースとした車両で、トライハートやオプティマに比べ横に広い印象の車両でした(写真は三島市消防本部の車両。更新済み)

なお、低床と高床の2車種がありましたが、乗り心地などは悪いようです(写真は富士市消防本部の車両。更新済み)

トラックベースで最大級と言えば、東京消防庁が導入したスーパーアンビュランスが思い浮かびます。
こちらは1台目(すでに更新済み)、2台目ともに三菱ふそうグレート(2台目はスーパーグレート)をベースにしており、傷病者の収容数も高規格救急車などよりはるかに大きいものとなっています。なお、東京消防庁には現在2台が在籍しており、第2方面隊ハイパーレスキューに2台目が、第8方面隊ハイパーレスキューには3台目(いすゞギガベース)が配備されています。
この他にも、マイクロバスをベースとした救急車が存在し、消防本部所属車両では東京消防庁第3方面隊ハイパーレスキューの車両と愛知県知多中部広域事務組合消防本部に配備されています。

こちらは病院のドクターカー。規模の大きい病院では、ドクターカーやNICU(新生児集中治療)としての車両で導入されることが多く、消防ではあまり見られないマイクロバスベースの救急車がいたりします。なお、最近では搬送を救急車にし、初期治療で医師が同行するケースが多くなってきたため、医師と初期治療設備を運ぶためだけのドクターカーが増えてきています。これらの車両はセダンタイプやステーションワゴンの車両またはRV車ベースの車両が多く、小回りが利く点ではマイクロバスなどに比べて優れています。
以上で、その1~その3まで特集しました救急車についての説明を終わります。
次回は、化学工場や規模が大きい油火災などで活躍する化学車を特集します。では
2013年11月28日
救急車 その2
こんにちは。前回に引き続き、今回も救急車の続きです。
前回トヨタの救急車の説明をしましたが、日産の救急車の紹介です。
・パラメディック
パラメディックは日産が作った高規格救急車です。1992年にアトラス20をベースに製作されましたが、1995年にアトラス20がいすゞからのOEMとなったため、日産オリジナルのアトラス顔からいすゞエルフ顔に変わりました。

マイナーチェンジ後の初代パラメディック(写真は浜松市消防局のもの。現在は更新済み)。国産高規格救急車としては初めてのトラックベースの車両でした。
そして、これと並走して1994年に登場したのがパラメディックⅡです。パラメディックはトラックベースのため室内空間の確保はできたものの、車体が大きく乗り心地が悪く搬送患者に影響を及ぼすこともありました。そのため、ワンボックスベースの高規格救急車として登場したのが本車です。

こちらがパラメディックⅡ(写真は三島市消防本部の車両)。4ナンバーのキャラバンでギリギリのスペースを有効活用しています。なお、高規格救急車の中では一番最少の車両であり、今でもこの車両より小さい高規格救急車はいません。
そして、パラメディックも1998年にフルモデルチェンジします。
今までパラメディックⅡとパラメディックの2車種で販売していたものを、フルモデルチェンジを機に両者を統合しパラメディックで統一しました。

こちらが2代目パラメディック(写真は静岡市消防局の車両)。正面はエルグランド、後ろはキャラバンの車体を使用した合造車で、ジャンボタクシーなどにもこの車体が流用されました。なお、パラメディックⅡもそうですが一部はいすゞにOEMとして供給され、スーパーメディック(パラメディックⅡのOEMはスーパーメディックⅡ)として販売されていました。

こちらがスーパーメディック(写真は静岡市消防局のもの。更新済み)。パラメディックとほぼ同じですが、車両屋根部の表記や装備ホイールの違いなど少ない点で違いがあります。
なお、日産の高規格救急車はマイナーチェンジをしているものの現在もこの2代目パラメディックを販売しており、国産高規格救急車としてはモデルとして一番長く販売されています。
・2B車両
トヨタと同じく、日産にも2Bタイプの救急車がいます。

E24キャラバンを使用した2B救急車。高規格救急車登場以前は、このタイプがかなりいました。写真は湖西市消防本部の車両(更新済み)

こちらが後期型タイプ。キャラバンホーミーの車体を使用したタイプで、現在でも予備車や病院の搬送車両として生き残っているものがいます(写真は磐田市消防本部の車両。更新済み)
以上で日産救急車勢の紹介を終わります。次回も救急車ネタでその他のメーカーの救急車を紹介します。
前回トヨタの救急車の説明をしましたが、日産の救急車の紹介です。
・パラメディック
パラメディックは日産が作った高規格救急車です。1992年にアトラス20をベースに製作されましたが、1995年にアトラス20がいすゞからのOEMとなったため、日産オリジナルのアトラス顔からいすゞエルフ顔に変わりました。

マイナーチェンジ後の初代パラメディック(写真は浜松市消防局のもの。現在は更新済み)。国産高規格救急車としては初めてのトラックベースの車両でした。
そして、これと並走して1994年に登場したのがパラメディックⅡです。パラメディックはトラックベースのため室内空間の確保はできたものの、車体が大きく乗り心地が悪く搬送患者に影響を及ぼすこともありました。そのため、ワンボックスベースの高規格救急車として登場したのが本車です。

こちらがパラメディックⅡ(写真は三島市消防本部の車両)。4ナンバーのキャラバンでギリギリのスペースを有効活用しています。なお、高規格救急車の中では一番最少の車両であり、今でもこの車両より小さい高規格救急車はいません。
そして、パラメディックも1998年にフルモデルチェンジします。
今までパラメディックⅡとパラメディックの2車種で販売していたものを、フルモデルチェンジを機に両者を統合しパラメディックで統一しました。

こちらが2代目パラメディック(写真は静岡市消防局の車両)。正面はエルグランド、後ろはキャラバンの車体を使用した合造車で、ジャンボタクシーなどにもこの車体が流用されました。なお、パラメディックⅡもそうですが一部はいすゞにOEMとして供給され、スーパーメディック(パラメディックⅡのOEMはスーパーメディックⅡ)として販売されていました。

こちらがスーパーメディック(写真は静岡市消防局のもの。更新済み)。パラメディックとほぼ同じですが、車両屋根部の表記や装備ホイールの違いなど少ない点で違いがあります。
なお、日産の高規格救急車はマイナーチェンジをしているものの現在もこの2代目パラメディックを販売しており、国産高規格救急車としてはモデルとして一番長く販売されています。
・2B車両
トヨタと同じく、日産にも2Bタイプの救急車がいます。

E24キャラバンを使用した2B救急車。高規格救急車登場以前は、このタイプがかなりいました。写真は湖西市消防本部の車両(更新済み)

こちらが後期型タイプ。キャラバンホーミーの車体を使用したタイプで、現在でも予備車や病院の搬送車両として生き残っているものがいます(写真は磐田市消防本部の車両。更新済み)
以上で日産救急車勢の紹介を終わります。次回も救急車ネタでその他のメーカーの救急車を紹介します。
2013年11月22日
救急車 その1
こんにちは。救助工作車の記事を更新後、仕事が忙しくなり更新している暇がありませんでした。申し訳ありません。
さて、今回解説する救急車は、誰でも知っている車両です。火を消すポンプ車や救助作業を行う救助工作車よりも出動回数が多く、首都東京を管轄する東京消防庁では48秒に1件、救急車1台当り1日7.7件出動しているほどです。
日本における最初の救急車は1931年に大阪に配備され、それ以降傷病者を病院に運ぶ任をしています。1991年以前は、救急隊が病院に傷病者を搬送するのを主としていましたが、法律の関係上救急隊員が医師でないため医療活動を行うことはできませんでした。そのため、1分1秒を争う場合病院に着いてからでは手遅れというケースも多く、また助かっても後遺症などの社会復帰に問題があるなどの点もありました。
そこで、1991年に救急救命士法が制定され、医師の指示の下、医療処置が行えるようになりました。これ以降救急車には順次医療処置ができる設備が搭載され、それまでの2B(ベッドが2つ)型救急車の他に高規格救急車と言う分類ができました。輸液や除細動(心肺蘇生)、薬剤投与など医療処置が行えることで、救命率は上がりました。また、これまでの2B救急車も高規格用の設備を搭載したものが登場し、こちらは準高規格救急車と言う分類になっています。
ポンプ車やタンク車などは消防車を作るメーカーが車両メーカーが作った車を艤装しますが、救急車はこれらのメーカーの他に車両メーカー自身が自社の車を艤装して作っている場合があります。
ではその1では、トヨタ車両を紹介します。
・ハイメディック(HIMEDIC)
ハイメディックはトヨタ自動車が作っている高規格救急車です。1991年の救急救命士法制定直後は、日本に高規格救急車がいなかったため、ベンツやフォードの車両をベースにした救急車がいましたが、車体が大きいが故狭い道の日本には使い勝手が悪く、また気候などから車両故障もしばしばありました。そして1992年に国産高規格救急車初として登場したのがハイメディックです。

こちらが初代ハイメディックです(写真は静岡市消防局のもの。廃車済み)。100系ハイエースをベースに、屋根をかさ上げし、室内高を確保しました。またエンジンもハイエースオリジナルのものではなく、セルシオ用のV形8気筒エンジンを搭載。独特な音をするサイレンと前面に書かれたエンジン形式を示すV8が特徴でした。現在はほとんどが廃車になっており、残っている車両も予備車として配備され、他は海外に譲渡され活躍されています。

1997年にフルモデルチェンジされ、新しく登場した2代目ハイメディックです(写真は静岡市消防局のもの)。初代は高規格として設備・車両性能を重視しすぎたあまりコストがかかり、車両価格が高くなってしまったことを踏まえ、コストダウンと使いやすさ向上を目標に作られました。その2で紹介する日産パラメディックと並び全国各地に配置され、また小回りできるように日本の救急車で初の4WSを採用しました。また、後期モデルでは輝度不足で実現が難しいとされていたLED赤色灯を小糸製作所と共同制作し、視認性が大幅にアップしました。こちらも現在は予備車に降格している車両が多いですが、地方都市ではまだ現役で活躍しているところもあります。

2006年に100系ハイエースがフルモデルチェンジするのとほぼ同時期にモデルチェンジしたのが3代目ハイメディックです(写真は峡南広域行政組合消防本部のもの)。2代目の4WS機能を省き、コストダウン化及び室内の空間確保がされました。こちらも登場当時から多くの消防本部で配備され、今も第一線で活躍しています。

こちらは大月市消防本部の3代目ハイメディック。赤いラインの配置が独特で、俗称ではウルトラマンとも言われているほどらしいです。

2010年にマイナーチェンジをした3代目ハイメディック(写真は富士五湖消防本部のもの)。フロントライトやバンパーの形状が変わりました。またフロントライトもHIDにできるようオプションが追加されました。

比較写真(共に富士市消防本部のもの)。向かって左側がマイナーチェンジ後の車両、右がマイナーチェンジ前の車両です。フロントライトの形状が違うのが分かります。
・2B車両(トヨタ)
高規格とは別に、昔からある普通救急車のことを指します。高規格救急車では値段が高すぎたり、狭い道などに入る際に車両サイズが大きすぎるなどの問題から、現在でも販売されています。なお、設備機器類は高規格に準じたものであるため、医療処置は高規格救急車と同様のことが行えます。しかし、ほとんどの消防本部が高規格救急車を入れているため、現存している車両はほとんどが予備車や病院の搬送車ばかりです。

100系ハイエースを使用した2B救急車は、高規格救急車が登場する以前に多く使われていたうちの1台のため、現在残っている古いタイプの中でも多い方に分類されます(写真は湖西市消防本部のもの。廃車済み)

こちらは後期型の100系ハイエースをベースとした2B救急車(写真は富士宮市消防本部のもの)

ハイメディックが1997年に2代目に移行したのち、2B救急車もフルモデルチェンジされました。写真のトヨタレジアスエースがベースの車両は、現存している2B救急車の中でも最も多いタイプと思われます(写真は富士市消防本部のもの。廃車済み)

2006年にハイメディックがフルモデルチェンジされたのに伴い、2Bも再びモデルチェンジました。車両外観はほとんど3代目ハイメディックと同じものにされています(写真は浜松市消防局のもの)
その1は以上で終わります。その2では日産の車輌を紹介したいと思います。では
さて、今回解説する救急車は、誰でも知っている車両です。火を消すポンプ車や救助作業を行う救助工作車よりも出動回数が多く、首都東京を管轄する東京消防庁では48秒に1件、救急車1台当り1日7.7件出動しているほどです。
日本における最初の救急車は1931年に大阪に配備され、それ以降傷病者を病院に運ぶ任をしています。1991年以前は、救急隊が病院に傷病者を搬送するのを主としていましたが、法律の関係上救急隊員が医師でないため医療活動を行うことはできませんでした。そのため、1分1秒を争う場合病院に着いてからでは手遅れというケースも多く、また助かっても後遺症などの社会復帰に問題があるなどの点もありました。
そこで、1991年に救急救命士法が制定され、医師の指示の下、医療処置が行えるようになりました。これ以降救急車には順次医療処置ができる設備が搭載され、それまでの2B(ベッドが2つ)型救急車の他に高規格救急車と言う分類ができました。輸液や除細動(心肺蘇生)、薬剤投与など医療処置が行えることで、救命率は上がりました。また、これまでの2B救急車も高規格用の設備を搭載したものが登場し、こちらは準高規格救急車と言う分類になっています。
ポンプ車やタンク車などは消防車を作るメーカーが車両メーカーが作った車を艤装しますが、救急車はこれらのメーカーの他に車両メーカー自身が自社の車を艤装して作っている場合があります。
ではその1では、トヨタ車両を紹介します。
・ハイメディック(HIMEDIC)
ハイメディックはトヨタ自動車が作っている高規格救急車です。1991年の救急救命士法制定直後は、日本に高規格救急車がいなかったため、ベンツやフォードの車両をベースにした救急車がいましたが、車体が大きいが故狭い道の日本には使い勝手が悪く、また気候などから車両故障もしばしばありました。そして1992年に国産高規格救急車初として登場したのがハイメディックです。

こちらが初代ハイメディックです(写真は静岡市消防局のもの。廃車済み)。100系ハイエースをベースに、屋根をかさ上げし、室内高を確保しました。またエンジンもハイエースオリジナルのものではなく、セルシオ用のV形8気筒エンジンを搭載。独特な音をするサイレンと前面に書かれたエンジン形式を示すV8が特徴でした。現在はほとんどが廃車になっており、残っている車両も予備車として配備され、他は海外に譲渡され活躍されています。

1997年にフルモデルチェンジされ、新しく登場した2代目ハイメディックです(写真は静岡市消防局のもの)。初代は高規格として設備・車両性能を重視しすぎたあまりコストがかかり、車両価格が高くなってしまったことを踏まえ、コストダウンと使いやすさ向上を目標に作られました。その2で紹介する日産パラメディックと並び全国各地に配置され、また小回りできるように日本の救急車で初の4WSを採用しました。また、後期モデルでは輝度不足で実現が難しいとされていたLED赤色灯を小糸製作所と共同制作し、視認性が大幅にアップしました。こちらも現在は予備車に降格している車両が多いですが、地方都市ではまだ現役で活躍しているところもあります。

2006年に100系ハイエースがフルモデルチェンジするのとほぼ同時期にモデルチェンジしたのが3代目ハイメディックです(写真は峡南広域行政組合消防本部のもの)。2代目の4WS機能を省き、コストダウン化及び室内の空間確保がされました。こちらも登場当時から多くの消防本部で配備され、今も第一線で活躍しています。

こちらは大月市消防本部の3代目ハイメディック。赤いラインの配置が独特で、俗称ではウルトラマンとも言われているほどらしいです。

2010年にマイナーチェンジをした3代目ハイメディック(写真は富士五湖消防本部のもの)。フロントライトやバンパーの形状が変わりました。またフロントライトもHIDにできるようオプションが追加されました。

比較写真(共に富士市消防本部のもの)。向かって左側がマイナーチェンジ後の車両、右がマイナーチェンジ前の車両です。フロントライトの形状が違うのが分かります。
・2B車両(トヨタ)
高規格とは別に、昔からある普通救急車のことを指します。高規格救急車では値段が高すぎたり、狭い道などに入る際に車両サイズが大きすぎるなどの問題から、現在でも販売されています。なお、設備機器類は高規格に準じたものであるため、医療処置は高規格救急車と同様のことが行えます。しかし、ほとんどの消防本部が高規格救急車を入れているため、現存している車両はほとんどが予備車や病院の搬送車ばかりです。

100系ハイエースを使用した2B救急車は、高規格救急車が登場する以前に多く使われていたうちの1台のため、現在残っている古いタイプの中でも多い方に分類されます(写真は湖西市消防本部のもの。廃車済み)

こちらは後期型の100系ハイエースをベースとした2B救急車(写真は富士宮市消防本部のもの)

ハイメディックが1997年に2代目に移行したのち、2B救急車もフルモデルチェンジされました。写真のトヨタレジアスエースがベースの車両は、現存している2B救急車の中でも最も多いタイプと思われます(写真は富士市消防本部のもの。廃車済み)

2006年にハイメディックがフルモデルチェンジされたのに伴い、2Bも再びモデルチェンジました。車両外観はほとんど3代目ハイメディックと同じものにされています(写真は浜松市消防局のもの)
その1は以上で終わります。その2では日産の車輌を紹介したいと思います。では
2013年09月11日
救助工作車
こんにちは。今回は前回予告していた通り、救助工作車のことについて説明したいと思います。
救助工作車とは、火を消すポンプ車とは違い人命救助のための車両になります。けが人を処置して病院に搬送するのは救急隊ですが、そのけが人が自力で脱出できない場合は救助隊が救うことになります。
その救うための機材を搭載し出動するのが救助工作車なのです。一般的に救助隊はオレンジの服を着て、他の部隊とは違う雰囲気を出しています。また、消防で一番憧れが多いのはやはり救助隊で、人気も一番あります。
さて救助工作車ですが、ポンプ車と同様にⅠ型~Ⅳ型までタイプがあります。
まずはⅠ型ですが、こちらは2~3tベースの小型トラックを用いた車両です。人口の少ない小規模自治体では使われていた車両ですが、近年はⅡ型もしくはポンプ車兼用車両としての導入が多く、Ⅰ型の救助工作車はほとんどありません。
次にⅡ型です。Ⅱ型は5t~7tベースのトラックを用いた車両で、今一番普及している車両です。Ⅱ型は一般災害及び救助事案に対応する資機材を搭載しており、後部にクレーンを搭載している車両もいます。

救助工作車Ⅱ型(写真は富士宮市消防本部中央消防署の車両)。前面にはウインチも搭載しており、後部にはクレーンも搭載しています。

こちらも救助工作車Ⅱ型(写真は甲府広域行政事務組合消防本部西消防署の車両)。こちらは平成2年に導入された車両で、総排気量が12000ccクラスなのでいすゞ810がベースの車両と思われる。車両的には8tクラスがベースと思われ、静岡県内にはこのサイズのⅡ型救助工作車はありません。
次にⅢ型です。Ⅲ型は震災対応の救助工作車で、Ⅱ型の救助資機材にくわえ高度救助資機材(二酸化炭素探査装置、画像探索機など)を搭載している車両が該当します。車体は7t~10tベースのトラック(震災対応のため、悪路走行を考慮し高床型を採用しているところが多い)を利用し、クレーンは標準装備しています。なお、車体がⅢ型に準じていても、クレーンを装備していなかったり、高度救助資機材を搭載していない場合はⅡ型に分類されます。

Ⅲ型の救助工作車(写真は富士市消防本部中央消防署の車両)。悪路の走行も考慮し、車高が高くなっています。

こちらは新潟市消防局中央消防署の車両。上記のⅢ型救助工作車と同様、車高の高い車両を使用していますが、こちらのベースは除雪車のトラックをベースにしています。

こちらは浜松市消防局中消防署鴨江出張所の救助工作車。車両は高床ではなく低床タイプですが、デッキ部分にFSV(FireSkyView)を採用しており、資機材の搭載及び上部視野の確保ができました。
最後にⅣ型。阪神大震災以降、震災対応車両としてⅢ型同様に開発された車両ですが、Ⅲ型と違うのは空路輸送も考慮されている点です。資機材はⅢ型に準じたものになっていますが、自衛隊のC-130輸送機には積むことができません。そのため、C-130に積めるようにするため、Ⅲ型の搭載資機材を2台の小型トラックに分散しました。これがⅣ型です。
Ⅳ型は2台一組のため、維持費などの関係やC-130での輸送が大震災などの災害時のみ(阪神大震災以降、震災時にC-130で輸送したケースは今のところない)のため、導入している自治体はそう多くありません。

Ⅳ型救助工作車(写真は浜松市消防局天竜消防署の車両)

Ⅳ型救助工作車(写真は浜松市消防局天竜消防署の車両)
この2台一組で行動します。なお、浜松市はⅣ型の救助工作車の片方にポンプ機能を搭載しており、火災にも対応しています。また、全国でⅣ型の救助工作車を導入しているのは、東京消防庁・名古屋市消防局、大阪府消防局、福岡市消防局、浜松市消防局、さいたま市消防局の6都市しかありません(2012年度に貸与された大規模震災用高度救助車はⅣ型ベースの車両と判断し除く)
以上、Ⅰ型~Ⅳ型の説明でした。では、少しだけ派生形を見てみましょう。

こちらは新潟市消防局西消防署小針出張所の車両。コードは小針Rですが、ポンプを搭載しているため主に火災対応で運用していると思われます。

こちらは田方消防本部南消防署の救助工作車。コードは田方45(撮影当時は42)で、ポンプ及び水槽も搭載しているようです。

こちらは島田市消防本部金谷消防署の救助工作車。こちらも水槽(950L)を搭載しており、交通事故・火災に対応しています。なお、某氏からの情報によると、破損によりこの車両はすでに廃車になっているとか。

こちらはすでに廃車になった島田市消防本部金谷消防署の救助工作車。車体は古いですが、Ⅱ型救助工作車に該当すると思われます。
以上で救助工作車の説明を終わります。次回は、赤い車両が並ぶ中で唯一白い色を纏い、一番出動件数が多い救急車について特集します。では
救助工作車とは、火を消すポンプ車とは違い人命救助のための車両になります。けが人を処置して病院に搬送するのは救急隊ですが、そのけが人が自力で脱出できない場合は救助隊が救うことになります。
その救うための機材を搭載し出動するのが救助工作車なのです。一般的に救助隊はオレンジの服を着て、他の部隊とは違う雰囲気を出しています。また、消防で一番憧れが多いのはやはり救助隊で、人気も一番あります。
さて救助工作車ですが、ポンプ車と同様にⅠ型~Ⅳ型までタイプがあります。
まずはⅠ型ですが、こちらは2~3tベースの小型トラックを用いた車両です。人口の少ない小規模自治体では使われていた車両ですが、近年はⅡ型もしくはポンプ車兼用車両としての導入が多く、Ⅰ型の救助工作車はほとんどありません。
次にⅡ型です。Ⅱ型は5t~7tベースのトラックを用いた車両で、今一番普及している車両です。Ⅱ型は一般災害及び救助事案に対応する資機材を搭載しており、後部にクレーンを搭載している車両もいます。

救助工作車Ⅱ型(写真は富士宮市消防本部中央消防署の車両)。前面にはウインチも搭載しており、後部にはクレーンも搭載しています。

こちらも救助工作車Ⅱ型(写真は甲府広域行政事務組合消防本部西消防署の車両)。こちらは平成2年に導入された車両で、総排気量が12000ccクラスなのでいすゞ810がベースの車両と思われる。車両的には8tクラスがベースと思われ、静岡県内にはこのサイズのⅡ型救助工作車はありません。
次にⅢ型です。Ⅲ型は震災対応の救助工作車で、Ⅱ型の救助資機材にくわえ高度救助資機材(二酸化炭素探査装置、画像探索機など)を搭載している車両が該当します。車体は7t~10tベースのトラック(震災対応のため、悪路走行を考慮し高床型を採用しているところが多い)を利用し、クレーンは標準装備しています。なお、車体がⅢ型に準じていても、クレーンを装備していなかったり、高度救助資機材を搭載していない場合はⅡ型に分類されます。

Ⅲ型の救助工作車(写真は富士市消防本部中央消防署の車両)。悪路の走行も考慮し、車高が高くなっています。

こちらは新潟市消防局中央消防署の車両。上記のⅢ型救助工作車と同様、車高の高い車両を使用していますが、こちらのベースは除雪車のトラックをベースにしています。

こちらは浜松市消防局中消防署鴨江出張所の救助工作車。車両は高床ではなく低床タイプですが、デッキ部分にFSV(FireSkyView)を採用しており、資機材の搭載及び上部視野の確保ができました。
最後にⅣ型。阪神大震災以降、震災対応車両としてⅢ型同様に開発された車両ですが、Ⅲ型と違うのは空路輸送も考慮されている点です。資機材はⅢ型に準じたものになっていますが、自衛隊のC-130輸送機には積むことができません。そのため、C-130に積めるようにするため、Ⅲ型の搭載資機材を2台の小型トラックに分散しました。これがⅣ型です。
Ⅳ型は2台一組のため、維持費などの関係やC-130での輸送が大震災などの災害時のみ(阪神大震災以降、震災時にC-130で輸送したケースは今のところない)のため、導入している自治体はそう多くありません。

Ⅳ型救助工作車(写真は浜松市消防局天竜消防署の車両)

Ⅳ型救助工作車(写真は浜松市消防局天竜消防署の車両)
この2台一組で行動します。なお、浜松市はⅣ型の救助工作車の片方にポンプ機能を搭載しており、火災にも対応しています。また、全国でⅣ型の救助工作車を導入しているのは、東京消防庁・名古屋市消防局、大阪府消防局、福岡市消防局、浜松市消防局、さいたま市消防局の6都市しかありません(2012年度に貸与された大規模震災用高度救助車はⅣ型ベースの車両と判断し除く)
以上、Ⅰ型~Ⅳ型の説明でした。では、少しだけ派生形を見てみましょう。

こちらは新潟市消防局西消防署小針出張所の車両。コードは小針Rですが、ポンプを搭載しているため主に火災対応で運用していると思われます。

こちらは田方消防本部南消防署の救助工作車。コードは田方45(撮影当時は42)で、ポンプ及び水槽も搭載しているようです。

こちらは島田市消防本部金谷消防署の救助工作車。こちらも水槽(950L)を搭載しており、交通事故・火災に対応しています。なお、某氏からの情報によると、破損によりこの車両はすでに廃車になっているとか。

こちらはすでに廃車になった島田市消防本部金谷消防署の救助工作車。車体は古いですが、Ⅱ型救助工作車に該当すると思われます。
以上で救助工作車の説明を終わります。次回は、赤い車両が並ぶ中で唯一白い色を纏い、一番出動件数が多い救急車について特集します。では
2013年09月07日
タンク車
こんにちは。
前回は「火を消す車」ということで、2種類の内のポンプ車に関しての記事を書かせていただきましたが、今回はもう一方のタンク車に関して書かせていただきます。
タンク車はポンプ車と基本的に同じ役割をしますが、大きな違いは水槽を積んでいるところです。
一般的に火を消すには水が必要です。しかし、到着場所に常に水利があるわけではなく、その場合その場所にもっとも近い水利から水を持ってこなければなりません。これでは、水を出すのに大幅に時間がかかってしまいますし、初期放水ができません。そのため、初期放水をするために水槽付きの車両が考えられ、水槽付きポンプ車「タンク車とも」と言われるようになりました。
タンク車にはⅠ型とⅡ型があり、Ⅰ型にはポンプ車同様ホイールベースの違いからⅠ-AとⅠ-B型の2種類に分けることができます。
まずはⅠ型から。Ⅰ型は水槽容量1500リットル以上の車両を規定しています。

こちらはⅠ-A型のタンク車です(写真は島田市消防本部金谷消防署川根南分遣所のタンク車)。I-A型は主にホースカー無の車両ですが、補助金の関係上ホイールベース3m以上、A-2級以上のポンプを搭載しています。

なお、近年では見栄えや機能性重視のため、すべてシャッター方式にする車両が増えています(写真は静岡市消防局千代田消防署しずはた出張所のタンク車)

こちらはⅠ-B型のタンク車です(写真は富士市消防本部西消防署のタンク車)。Ⅰ-B形はホースカーを搭載している点がⅠ-A型と大きく異なる点になります。ちなみにこちらも補助金の関係上、ホイールベース3.5m以上、A-2級以上のポンプを搭載しているという国の規格に則った車両がほとんどです。
ちなみにホースカーとは、名前の通りホースを搭載した車両です。火災現場でホースを延長する際に人間が一度に持てるホースの束には限界があります。そこでホースカーにホースを搭載し、それを延長することによって無駄な手間をなくすことができるのです。
お次はⅡ型。Ⅱ型は水槽容量2000リットル以上の車両を規定しています。

Ⅱ型タンク車(写真は甲府市広域行政組合消防本部中央消防署のタンク車)。ホースカーを搭載しているもの、していないもの関わらず、2t以上の水槽を搭載していればⅡ型に分類されます。ポンプの機能はⅠ型同様A-2級以上のポンプを搭載していることが前提です。

こちらもⅡ型のタンク車(写真は浜松市消防局中消防署のタンク車)。5t水槽を搭載するため、車体は2t水槽の車両よりも大きなもの(7t~8tシャーシ)を使用しています。
タンク車の基本的な説明は以上です。では少しだけ派生型を見てみましょう。

こちらは磐田市消防本部磐田消防署豊田分遣所にいるⅠ-A型タンク車。ホースカーは搭載していませんが、救助資機材も搭載しており、交通事故事案などにも対応できます。

こちらも同様、Ⅰ-A型のタンク車。前面表記もある通り、こちらは純粋に救助工作車として運用していますが、元々はタンク車なので火災事案にも出動ができると思われます。ちなみに所属は静岡市消防局湾岸消防署庵原分署の車両で、元は静岡市消防局追手町消防署のタンク車として運用されていました(途中の湾岸PR運用は除く)
以上で、タンク車の説明を終わります。次回は・・・様々な分野で人命救助を行い、憧れのオレンジ服の隊員が乗る救助工作車をご説明します
前回は「火を消す車」ということで、2種類の内のポンプ車に関しての記事を書かせていただきましたが、今回はもう一方のタンク車に関して書かせていただきます。
タンク車はポンプ車と基本的に同じ役割をしますが、大きな違いは水槽を積んでいるところです。
一般的に火を消すには水が必要です。しかし、到着場所に常に水利があるわけではなく、その場合その場所にもっとも近い水利から水を持ってこなければなりません。これでは、水を出すのに大幅に時間がかかってしまいますし、初期放水ができません。そのため、初期放水をするために水槽付きの車両が考えられ、水槽付きポンプ車「タンク車とも」と言われるようになりました。
タンク車にはⅠ型とⅡ型があり、Ⅰ型にはポンプ車同様ホイールベースの違いからⅠ-AとⅠ-B型の2種類に分けることができます。
まずはⅠ型から。Ⅰ型は水槽容量1500リットル以上の車両を規定しています。

こちらはⅠ-A型のタンク車です(写真は島田市消防本部金谷消防署川根南分遣所のタンク車)。I-A型は主にホースカー無の車両ですが、補助金の関係上ホイールベース3m以上、A-2級以上のポンプを搭載しています。

なお、近年では見栄えや機能性重視のため、すべてシャッター方式にする車両が増えています(写真は静岡市消防局千代田消防署しずはた出張所のタンク車)

こちらはⅠ-B型のタンク車です(写真は富士市消防本部西消防署のタンク車)。Ⅰ-B形はホースカーを搭載している点がⅠ-A型と大きく異なる点になります。ちなみにこちらも補助金の関係上、ホイールベース3.5m以上、A-2級以上のポンプを搭載しているという国の規格に則った車両がほとんどです。
ちなみにホースカーとは、名前の通りホースを搭載した車両です。火災現場でホースを延長する際に人間が一度に持てるホースの束には限界があります。そこでホースカーにホースを搭載し、それを延長することによって無駄な手間をなくすことができるのです。
お次はⅡ型。Ⅱ型は水槽容量2000リットル以上の車両を規定しています。

Ⅱ型タンク車(写真は甲府市広域行政組合消防本部中央消防署のタンク車)。ホースカーを搭載しているもの、していないもの関わらず、2t以上の水槽を搭載していればⅡ型に分類されます。ポンプの機能はⅠ型同様A-2級以上のポンプを搭載していることが前提です。

こちらもⅡ型のタンク車(写真は浜松市消防局中消防署のタンク車)。5t水槽を搭載するため、車体は2t水槽の車両よりも大きなもの(7t~8tシャーシ)を使用しています。
タンク車の基本的な説明は以上です。では少しだけ派生型を見てみましょう。

こちらは磐田市消防本部磐田消防署豊田分遣所にいるⅠ-A型タンク車。ホースカーは搭載していませんが、救助資機材も搭載しており、交通事故事案などにも対応できます。

こちらも同様、Ⅰ-A型のタンク車。前面表記もある通り、こちらは純粋に救助工作車として運用していますが、元々はタンク車なので火災事案にも出動ができると思われます。ちなみに所属は静岡市消防局湾岸消防署庵原分署の車両で、元は静岡市消防局追手町消防署のタンク車として運用されていました(途中の湾岸PR運用は除く)
以上で、タンク車の説明を終わります。次回は・・・様々な分野で人命救助を行い、憧れのオレンジ服の隊員が乗る救助工作車をご説明します
2013年08月27日
ポンプ車
こんにちは。
初回は、総務省消防庁貸与車両に関して書かせていただきましたが、今回は一般の消防署や消防団にもいるポンプ車についてスポットを当ててみます。
なお、次回以降消防車シリーズをカテゴリ分けしてしばらく説明していく予定ですので、ご期待に(しないでください
さて、ポンプ車とは何かと言われて即答するならば、「火を消す車」というべきでしょうか?
消防は消火の他に、救急や救助などの役割がありますが、車両の分布から見れば消火する車両が多いのです。
消防車がたくさんいる消防署がありますが、それ以上にその消防署の下に分遣所や出張所があります。これらは警察でいう交番のようなものに例えられます。会社内で例えば、☆☆ガスの○○支社××営業所のような感じです。
つまり、大きな消防署1つに対して、小さな分遣所や出張所がいくつかあり、それぞれの管内の消防署がその管内にある分遣所や出張所を管理しています。
この出張所には一般的にポンプ車と救急車が配備されていますが、人口比率や人員配置、あるいは消防力の関係からポンプ車しかいないところもあります。
沼津市を例に例えてみると、沼津市南西部(この西は伊豆半島側を指します)を管轄する南消防署というものがあります。南消防署が官轄する署に静浦分遣所、大平分遣所、内浦分遣所、西浦分遣所、戸田分遣所があります。しかし、このうち救急車がいるのは静浦分遣所と内浦分遣所、戸田分遣所の3署で、大平分遣所と戸田分遣所には救急車はおらずポンプ車しかいません。なお、内浦分遣所管内で救急要請があった場合西浦分遣所か静浦分遣所の救急隊が、大平分遣所管内で救急要請があった場合は、静浦分遣所か南消防署の救急隊が出動することになります。
このことから、普通は救急車よりポンプ車の方が多く配備されることが理解できたと思います。
さて、ポンプ車はポンプ車でも大きく二つの種類に分けることができます。
まず一つは普通ポンプ車です。こちらはポンプだけの車両で、消火時は近くの消防水利から水をくみ上げ放水します。近年では、人員の関係からポンプ車だけでなく簡易的な救助資機材も搭載し、救助車兼用のところもあります。

こちらが一般的なポンプ車です(写真は、甲府広域行政事務組合消防本部中央消防署湯村出張所の車両)。これはCD-1型と呼ばれるタイプで、Cはキャブオーバー、Dはダブルデッキ(ドアが両側で計4枚)、1はポンプ車の大きさでホイルベースが2m以上、B1級以上の性能を持つポンプを搭載している車両です。なお、消防団のポンプ車も大半はこのCD-1型タイプが多いです。
現在ではCAFS(Compressed Air Foam System:圧縮空気泡消火システム)を搭載した車両も普及してきています。

なお、ポンプ車専用の車体が作られたことがありました(写真は浜松市消防局南消防署白脇出張所のポンプ車)

こちらがCAFS搭載のポンプ車(写真は浜松市消防局東消防署上石田出張所の車両)。CAFSの原理としては、水に少量の消火剤を混ぜ、それを圧縮空気とともに放水することで、水の拡散率を高め、消火効率をよくしたものです。このため、一般のタンク車(後述に記載)に比べて水の消費量も抑えることができます。なお、CD-1型区分ですが水槽は搭載しており、600Lが一般的となっています。

こちらがCD-2型のポンプ車です。基本的にCD-1型ポンプ車と同じですが、ホイールベースが3m以上、ポンプ性能がA-2級以上の車両のことを指します。見た目では、後述のⅠ型タンク車と見分けが付きにくい車両でもあります。

こちらはBD-1型。Bはボンネット型を、Dはダブルキャブを指しており、1はCD-1型と同様です。
昔はトラックがボンネット型が多いことや、ピックアップトラックを使用した方が悪路での走行がいいため、このような区分ができました。しかし、近年はピックアップトラックベースの車両がなくなってきたこと、またボンネットがあることで後部資機材部分がトラックに比べて劣ることから、製造されなくなりました。現存する車両も更新時期を迎えつつある古い車両ばかりのため、近い未来に区分消滅してしまう可能性が高いと思います。
ポンプ車の説明は以上ですが、少しだけ消火機能以外を搭載した車両を見てみましょう。

こちらは富士宮市消防本部西消防署のCD-2型ポンプ車。もちろん見た目はポンプ車ですが、資機材に救助資機材も搭載しており、交通事故などの救助にも出動することが可能です。

こちらは大月市消防本部大月消防署丹波山出張所のCD-1型ポンプ車。山間部を管轄するため、高床式の車体をベースにしており、バンパー部分には牽引用のウインチが搭載されています。また、救助資機材も搭載しているため、火災だけでなく救助事案にも出動できるようになっています。
以上、ポンプ車特集でした。次回はもう一つのタイプ、タンク車を紹介します。
では
初回は、総務省消防庁貸与車両に関して書かせていただきましたが、今回は一般の消防署や消防団にもいるポンプ車についてスポットを当ててみます。
なお、次回以降消防車シリーズをカテゴリ分けしてしばらく説明していく予定ですので、ご期待に(しないでください
さて、ポンプ車とは何かと言われて即答するならば、「火を消す車」というべきでしょうか?
消防は消火の他に、救急や救助などの役割がありますが、車両の分布から見れば消火する車両が多いのです。
消防車がたくさんいる消防署がありますが、それ以上にその消防署の下に分遣所や出張所があります。これらは警察でいう交番のようなものに例えられます。会社内で例えば、☆☆ガスの○○支社××営業所のような感じです。
つまり、大きな消防署1つに対して、小さな分遣所や出張所がいくつかあり、それぞれの管内の消防署がその管内にある分遣所や出張所を管理しています。
この出張所には一般的にポンプ車と救急車が配備されていますが、人口比率や人員配置、あるいは消防力の関係からポンプ車しかいないところもあります。
沼津市を例に例えてみると、沼津市南西部(この西は伊豆半島側を指します)を管轄する南消防署というものがあります。南消防署が官轄する署に静浦分遣所、大平分遣所、内浦分遣所、西浦分遣所、戸田分遣所があります。しかし、このうち救急車がいるのは静浦分遣所と内浦分遣所、戸田分遣所の3署で、大平分遣所と戸田分遣所には救急車はおらずポンプ車しかいません。なお、内浦分遣所管内で救急要請があった場合西浦分遣所か静浦分遣所の救急隊が、大平分遣所管内で救急要請があった場合は、静浦分遣所か南消防署の救急隊が出動することになります。
このことから、普通は救急車よりポンプ車の方が多く配備されることが理解できたと思います。
さて、ポンプ車はポンプ車でも大きく二つの種類に分けることができます。
まず一つは普通ポンプ車です。こちらはポンプだけの車両で、消火時は近くの消防水利から水をくみ上げ放水します。近年では、人員の関係からポンプ車だけでなく簡易的な救助資機材も搭載し、救助車兼用のところもあります。

こちらが一般的なポンプ車です(写真は、甲府広域行政事務組合消防本部中央消防署湯村出張所の車両)。これはCD-1型と呼ばれるタイプで、Cはキャブオーバー、Dはダブルデッキ(ドアが両側で計4枚)、1はポンプ車の大きさでホイルベースが2m以上、B1級以上の性能を持つポンプを搭載している車両です。なお、消防団のポンプ車も大半はこのCD-1型タイプが多いです。
現在ではCAFS(Compressed Air Foam System:圧縮空気泡消火システム)を搭載した車両も普及してきています。

なお、ポンプ車専用の車体が作られたことがありました(写真は浜松市消防局南消防署白脇出張所のポンプ車)

こちらがCAFS搭載のポンプ車(写真は浜松市消防局東消防署上石田出張所の車両)。CAFSの原理としては、水に少量の消火剤を混ぜ、それを圧縮空気とともに放水することで、水の拡散率を高め、消火効率をよくしたものです。このため、一般のタンク車(後述に記載)に比べて水の消費量も抑えることができます。なお、CD-1型区分ですが水槽は搭載しており、600Lが一般的となっています。

こちらがCD-2型のポンプ車です。基本的にCD-1型ポンプ車と同じですが、ホイールベースが3m以上、ポンプ性能がA-2級以上の車両のことを指します。見た目では、後述のⅠ型タンク車と見分けが付きにくい車両でもあります。

こちらはBD-1型。Bはボンネット型を、Dはダブルキャブを指しており、1はCD-1型と同様です。
昔はトラックがボンネット型が多いことや、ピックアップトラックを使用した方が悪路での走行がいいため、このような区分ができました。しかし、近年はピックアップトラックベースの車両がなくなってきたこと、またボンネットがあることで後部資機材部分がトラックに比べて劣ることから、製造されなくなりました。現存する車両も更新時期を迎えつつある古い車両ばかりのため、近い未来に区分消滅してしまう可能性が高いと思います。
ポンプ車の説明は以上ですが、少しだけ消火機能以外を搭載した車両を見てみましょう。

こちらは富士宮市消防本部西消防署のCD-2型ポンプ車。もちろん見た目はポンプ車ですが、資機材に救助資機材も搭載しており、交通事故などの救助にも出動することが可能です。

こちらは大月市消防本部大月消防署丹波山出張所のCD-1型ポンプ車。山間部を管轄するため、高床式の車体をベースにしており、バンパー部分には牽引用のウインチが搭載されています。また、救助資機材も搭載しているため、火災だけでなく救助事案にも出動できるようになっています。
以上、ポンプ車特集でした。次回はもう一つのタイプ、タンク車を紹介します。
では
2013年08月21日
総務省消防庁車両群
初記事になります。普段は本家「東海の部屋」で記事を書くので、こちらにはあまり書きませんがよろしくお願いします。
では、さっそくですが今回は総務省消防庁からの貸与車両についてまとめてみました。
そもそも、総務省消防庁は簡単に言ってしまえば、日本の消防行政の企画・立案、各種法令・基準の策定をするところで、国の総務省の外局にあたる機関です。つまり、直接的に各自治体の消防本部に対しては助言や補助などしかできず、また火災や災害事案に対して実際に活動を行うわけでもありません。
身近なところで例えれば、トイレの水漏れが起きたからといって市役所の人が直接直しに来るわけではありません。直しに来るのは、その市の認定工事店である水道屋が直接直します。市役所の人は、あくまでその水道屋に対して大まかな規定や方針を助言することしかできません。今回の場合、市役所が総務省消防庁、水道屋が各消防本部になります。
話を戻しますが、総務省消防庁の行っている規格の中で、消防車両の無料貸与制度というものがあります。
消防庁の広報では、「緊急消防援助隊の活動に必要な装備等のうち、地方公共団体による整備が費用対効果の面から非効率的なものについて、この無償使用制度を活用し、各都道府県の代表消防機関等へ全国的に配備しています」と書いてあります。
何を言っているのぞやと思う方が多いと思うので、詳しく説明を加えます。
そもそも、阪神淡路大震災や東日本大震災などが発生した場合、災害地区の消防本部も大きな損害を受けます。例えば阪神淡路大震災の場合では火災、東日本大震災の場合は津波で消防本部が壊滅状態に陥り、消防車両も使えない状況に陥ります。その際に、他県の消防がその災害の救助や消火を行う必要があります。この部隊を緊急援助隊といいます。
もちろん、緊急援助隊というのは各県どの部隊をどれだけ出すかをあらかじめ規定しているためすべての車両が行くわけではありません。つまり静岡県で例えるならば、ポンプ隊は島田市と沼津市、救助隊は浜松市と静岡市、救急隊は富士市と志太広域消防本部(焼津市と藤枝市)というふうに決められています。
次に援助隊に必要な装備などのうち、費用対効果から非効率的なものと言う欄について説明します。
そもそも、消防車両は市の税金から購入されています。その中でも最も使用頻度の高い車両、つまりは怪我や病気などで病院まで搬送する救急車、火災などで出動するポンプ車などは費用対効果から効率的と言えます。
逆に、震災などで使用する重機、夜間の照明などに使用する照明電源車は特殊的な用途にしか使用できず、これは費用対効果から非効率的といえます。
しかし、大災害が起きればこのような非効率車両は重要視されます。重機などは倒壊した建造物破片などを撤去するのに使えますし、照明電源車は夜通しの活動などで明かりを灯し、電気が使用できない場所では電源車としての役割も果たせます。
普段はあまり使用しなくとも、いざというときは必需品となる。この文章はこれを説明しています。しかし、市の予算は毎年限られており、なおかつ1台数千万もする車両を簡単に買うことはできません。
そこで、このような特殊車両を大規模な消防本部(人口が多く予算が小都市に比べて多い場所)や政令指定都市などに国から無償提供することで、大災害発生時に緊急援助隊として活動できるようにというのが、車両貸与制度になります。
普通各消防署には先も書きましたが、救急車やポンプ車、救助工作車や大型水槽車、資機材搬送車や指揮車が置いてありますが、国から貸与車両はこのようなポピュラーな車両ではなく、普段は見ない特殊車両が貸し与えられています。その一部をご紹介します。

特殊災害対策車。NBC(Nuclear、Biological、Chemicalの頭文字。核・生物・化学の意)災害用に制作された車両です。人体に有害な物質が流出または故意に捲かれた場合、それを処理する必要があります。しかし、それが何の物質なのか分からなければ、除去する消防隊にも危険が及びますし、大きな2次災害を起こす可能性があります。その物質を分析するのがこの車両です。中には陽圧室と言うものがあり、外気を中に入れないような構造になっています。政令指定都市などに配備され、静岡県では静岡市消防局千代田消防署、浜松市消防局中消防署鴨江出張所に配備されています。また、NBC災害は最近増加傾向にあるため、各自治体でも自前で入れるようになってきています。

大型除染システム車。上記の特殊災害対策車は、NBC災害の分析を主にしますが、こちらの車両は人体などに付着した汚染物質を除去するための車両です。外観は資機材搬送車ですが、背中のコンテナには大型除染システムのテントなどが入っています。原理としては、テント内に脱衣室・洗浄レーン(歩行可能者レーン2つと歩行不可能者レーン1つ)、着衣室の3つに分かれており、流水による汚染物質の除去をこの中で行います。なお、脱衣・洗浄・着衣の行為を1つとして1時間に200人以上の対応ができるようになっています。静岡県では特殊災害対策車と同じ都市で同じ場所に配備されています。なお、東京消防庁ではテントではなく車両内に除去システムを搭載したものがあります。

特別高度救助車。トラック荷台には大型の扇風機のようなブロアーとウォーターカッターと言う資機材を搭載する小型コンテナが積んであります。ブロアーに関しては、送風だけでなく噴霧放水も可能です。火災時の排煙能力のだけでなく、気体状の危険物質(ガスなど)の排除のほか、フラッシュオーバー防止のための冷却送風の役割を兼ねています。ウォーターカッターは、エンジンカッターなど火花による切断が危険な状況下において、高圧の水を切断物質に充てることでドアなどの切断が行なえます。東京消防庁や大阪府消防局などには、ブロアー車とウォーターカッター車と言う風に別々に配備されていましたが、その後1台の車両に集約されこの車両に至ります。静岡県では、静岡市消防局清水消防署と浜松市消防局東消防署上石田出張所にそれぞれ配備されています。

なお、初期の車両は三菱ファイターがベース車両、現在の車両は上記のいすゞフォワードがベースとなっています。

支援車(1型)です。大災害時に、現場での長期活動を予測し、隊員の衣食住となる部屋の代わりになる車両です。もちろん、物資の搬送も可能で、カートに入れた資機材を運搬することもできます。荷台はドア部が左右に広がるようになっており、キッチン・浴室・洗面などが中に搭載されています。1次車は全国47都道府県に各1台ずつ配備され、静岡県では浜松市消防局北消防署曳馬野出張所に、山梨県では峡北広域行政組合消防本部韮崎消防署に配備されています。なお、総務省消防庁が必要とみなした都市に関しては、2次車が増車され配備されました。

送水車。別名「海水利用型水利システム車」とも言われるこの車両は、2km先まで最大4000L/minの水を送ることのできる車両です。震災などで消火栓が破壊された場合、消火用の水利を確保できません。そのため、この車両が海などの無限水利に隣接し、ポンプをおろして送水します。静岡県では浜松市消防局中消防署に配備されました。

ホース延長車。上記の送水車と2台1組で活動する車両です。荷台には、150mmのホースが2000m搭載されており、送水車が送る水をこの車両の搭載するホースを延長経由させます。静岡県では送水車同様浜松市消防局中消防署に配備されました。

都道府県指揮隊車。緊急援助隊には各都道府県分に出動しますが、その県ごとの隊を指揮する指揮隊も出動します。これは所轄署の指揮隊とは別に、緊急援助隊用の指揮隊(兼任しているところもあるが)として運行されます。静岡や山梨は千用の車両を持っていたのですが、もちろん所轄指揮車を利用しているところもあります。そのため、国で規格化した車両を貸与するに至りました。全国47都道府県に各1台が配備され、静岡県では静岡市消防局石田消防署に、山梨県では甲府広域行政事務組合消防本部南消防署に配備されました。

燃料補給車。災害時、長時間の車両活動により、消防車両などの燃料欠乏を防止するために作成されました。全国配備とはいきませんが、大規模都市や政令指定都市を中心に30台配備されました。静岡県では静岡市消防局追手町消防署平和出張所に配備されました。ちなみに、東京消防庁と横浜市消防局は自前でこの車両を購入しています。

資機材搬送車。先の人員輸送車とほぼセットで導入された車両です。車高が高いのは、悪路でも物資を運べるようにとのことで高床型となりました。リアにはパワーゲートもついており、重い荷物でも積み下ろしができます、全国で46台が配備され、静岡県では御殿場・小山広域消防組合消防本部御殿場消防署に山梨県では大月市消防本部大月消防署に配備されました。

重機運搬車。建造物の倒壊による道路障害や、重量物の撤去などに必要なショベルカーを運ぶ車両です。3型と5型の2種類があり、5型の方がショベルカーの大きさは大きいです。他、ショベルカーには放水銃もついており、ホースをつないで供給すれば放水することもできます。静岡県では、静岡市消防局清水消防署に配備されました。

こちらが、ショベルカーになります。もちろん、アームのアタッチメントも数種類搭載されています。

大規模災害用救助車。大規模災害時に、通常の震災対応の救助工作車と同様の働きをします。なお、車両はⅣ型の救助工作車に準じていますが、装備品は大きく異なり電気式救助機器を装備したERと空気圧式救助機器を搭載したARの2台一組で活動を行います。写真はERタイプ。

こちらはARタイプ。全国に3セットが配備され、うち1セットは静岡県浜松市消防局北消防署に配備されました。
他にも、無線中継車がありますがこちらは静岡県にも山梨県にも配備されなかったため、割愛させてもらいます。
このように特殊災害用の車両が国から無償で提供されることは喜ばしいことですが、配備先の消防本部は部隊用の人員を割かなければならない、緊急援助隊出動時には必ず出動しなければならないなど、負担が大きくなる側面も持っています。
人が少ない消防本部では、提供を断らなければならない事態になる可能性もあります。
無償提供の良し悪しも含めて、今後の消防の課題の一つになっていくと考えられます。
長文になりましたが、初更新はこれで終わります。ここまでお読みいただき、ありがとうございました~
では、さっそくですが今回は総務省消防庁からの貸与車両についてまとめてみました。
そもそも、総務省消防庁は簡単に言ってしまえば、日本の消防行政の企画・立案、各種法令・基準の策定をするところで、国の総務省の外局にあたる機関です。つまり、直接的に各自治体の消防本部に対しては助言や補助などしかできず、また火災や災害事案に対して実際に活動を行うわけでもありません。
身近なところで例えれば、トイレの水漏れが起きたからといって市役所の人が直接直しに来るわけではありません。直しに来るのは、その市の認定工事店である水道屋が直接直します。市役所の人は、あくまでその水道屋に対して大まかな規定や方針を助言することしかできません。今回の場合、市役所が総務省消防庁、水道屋が各消防本部になります。
話を戻しますが、総務省消防庁の行っている規格の中で、消防車両の無料貸与制度というものがあります。
消防庁の広報では、「緊急消防援助隊の活動に必要な装備等のうち、地方公共団体による整備が費用対効果の面から非効率的なものについて、この無償使用制度を活用し、各都道府県の代表消防機関等へ全国的に配備しています」と書いてあります。
何を言っているのぞやと思う方が多いと思うので、詳しく説明を加えます。
そもそも、阪神淡路大震災や東日本大震災などが発生した場合、災害地区の消防本部も大きな損害を受けます。例えば阪神淡路大震災の場合では火災、東日本大震災の場合は津波で消防本部が壊滅状態に陥り、消防車両も使えない状況に陥ります。その際に、他県の消防がその災害の救助や消火を行う必要があります。この部隊を緊急援助隊といいます。
もちろん、緊急援助隊というのは各県どの部隊をどれだけ出すかをあらかじめ規定しているためすべての車両が行くわけではありません。つまり静岡県で例えるならば、ポンプ隊は島田市と沼津市、救助隊は浜松市と静岡市、救急隊は富士市と志太広域消防本部(焼津市と藤枝市)というふうに決められています。
次に援助隊に必要な装備などのうち、費用対効果から非効率的なものと言う欄について説明します。
そもそも、消防車両は市の税金から購入されています。その中でも最も使用頻度の高い車両、つまりは怪我や病気などで病院まで搬送する救急車、火災などで出動するポンプ車などは費用対効果から効率的と言えます。
逆に、震災などで使用する重機、夜間の照明などに使用する照明電源車は特殊的な用途にしか使用できず、これは費用対効果から非効率的といえます。
しかし、大災害が起きればこのような非効率車両は重要視されます。重機などは倒壊した建造物破片などを撤去するのに使えますし、照明電源車は夜通しの活動などで明かりを灯し、電気が使用できない場所では電源車としての役割も果たせます。
普段はあまり使用しなくとも、いざというときは必需品となる。この文章はこれを説明しています。しかし、市の予算は毎年限られており、なおかつ1台数千万もする車両を簡単に買うことはできません。
そこで、このような特殊車両を大規模な消防本部(人口が多く予算が小都市に比べて多い場所)や政令指定都市などに国から無償提供することで、大災害発生時に緊急援助隊として活動できるようにというのが、車両貸与制度になります。
普通各消防署には先も書きましたが、救急車やポンプ車、救助工作車や大型水槽車、資機材搬送車や指揮車が置いてありますが、国から貸与車両はこのようなポピュラーな車両ではなく、普段は見ない特殊車両が貸し与えられています。その一部をご紹介します。

特殊災害対策車。NBC(Nuclear、Biological、Chemicalの頭文字。核・生物・化学の意)災害用に制作された車両です。人体に有害な物質が流出または故意に捲かれた場合、それを処理する必要があります。しかし、それが何の物質なのか分からなければ、除去する消防隊にも危険が及びますし、大きな2次災害を起こす可能性があります。その物質を分析するのがこの車両です。中には陽圧室と言うものがあり、外気を中に入れないような構造になっています。政令指定都市などに配備され、静岡県では静岡市消防局千代田消防署、浜松市消防局中消防署鴨江出張所に配備されています。また、NBC災害は最近増加傾向にあるため、各自治体でも自前で入れるようになってきています。

大型除染システム車。上記の特殊災害対策車は、NBC災害の分析を主にしますが、こちらの車両は人体などに付着した汚染物質を除去するための車両です。外観は資機材搬送車ですが、背中のコンテナには大型除染システムのテントなどが入っています。原理としては、テント内に脱衣室・洗浄レーン(歩行可能者レーン2つと歩行不可能者レーン1つ)、着衣室の3つに分かれており、流水による汚染物質の除去をこの中で行います。なお、脱衣・洗浄・着衣の行為を1つとして1時間に200人以上の対応ができるようになっています。静岡県では特殊災害対策車と同じ都市で同じ場所に配備されています。なお、東京消防庁ではテントではなく車両内に除去システムを搭載したものがあります。

特別高度救助車。トラック荷台には大型の扇風機のようなブロアーとウォーターカッターと言う資機材を搭載する小型コンテナが積んであります。ブロアーに関しては、送風だけでなく噴霧放水も可能です。火災時の排煙能力のだけでなく、気体状の危険物質(ガスなど)の排除のほか、フラッシュオーバー防止のための冷却送風の役割を兼ねています。ウォーターカッターは、エンジンカッターなど火花による切断が危険な状況下において、高圧の水を切断物質に充てることでドアなどの切断が行なえます。東京消防庁や大阪府消防局などには、ブロアー車とウォーターカッター車と言う風に別々に配備されていましたが、その後1台の車両に集約されこの車両に至ります。静岡県では、静岡市消防局清水消防署と浜松市消防局東消防署上石田出張所にそれぞれ配備されています。

なお、初期の車両は三菱ファイターがベース車両、現在の車両は上記のいすゞフォワードがベースとなっています。

支援車(1型)です。大災害時に、現場での長期活動を予測し、隊員の衣食住となる部屋の代わりになる車両です。もちろん、物資の搬送も可能で、カートに入れた資機材を運搬することもできます。荷台はドア部が左右に広がるようになっており、キッチン・浴室・洗面などが中に搭載されています。1次車は全国47都道府県に各1台ずつ配備され、静岡県では浜松市消防局北消防署曳馬野出張所に、山梨県では峡北広域行政組合消防本部韮崎消防署に配備されています。なお、総務省消防庁が必要とみなした都市に関しては、2次車が増車され配備されました。

送水車。別名「海水利用型水利システム車」とも言われるこの車両は、2km先まで最大4000L/minの水を送ることのできる車両です。震災などで消火栓が破壊された場合、消火用の水利を確保できません。そのため、この車両が海などの無限水利に隣接し、ポンプをおろして送水します。静岡県では浜松市消防局中消防署に配備されました。

ホース延長車。上記の送水車と2台1組で活動する車両です。荷台には、150mmのホースが2000m搭載されており、送水車が送る水をこの車両の搭載するホースを延長経由させます。静岡県では送水車同様浜松市消防局中消防署に配備されました。

都道府県指揮隊車。緊急援助隊には各都道府県分に出動しますが、その県ごとの隊を指揮する指揮隊も出動します。これは所轄署の指揮隊とは別に、緊急援助隊用の指揮隊(兼任しているところもあるが)として運行されます。静岡や山梨は千用の車両を持っていたのですが、もちろん所轄指揮車を利用しているところもあります。そのため、国で規格化した車両を貸与するに至りました。全国47都道府県に各1台が配備され、静岡県では静岡市消防局石田消防署に、山梨県では甲府広域行政事務組合消防本部南消防署に配備されました。

燃料補給車。災害時、長時間の車両活動により、消防車両などの燃料欠乏を防止するために作成されました。全国配備とはいきませんが、大規模都市や政令指定都市を中心に30台配備されました。静岡県では静岡市消防局追手町消防署平和出張所に配備されました。ちなみに、東京消防庁と横浜市消防局は自前でこの車両を購入しています。

資機材搬送車。先の人員輸送車とほぼセットで導入された車両です。車高が高いのは、悪路でも物資を運べるようにとのことで高床型となりました。リアにはパワーゲートもついており、重い荷物でも積み下ろしができます、全国で46台が配備され、静岡県では御殿場・小山広域消防組合消防本部御殿場消防署に山梨県では大月市消防本部大月消防署に配備されました。

重機運搬車。建造物の倒壊による道路障害や、重量物の撤去などに必要なショベルカーを運ぶ車両です。3型と5型の2種類があり、5型の方がショベルカーの大きさは大きいです。他、ショベルカーには放水銃もついており、ホースをつないで供給すれば放水することもできます。静岡県では、静岡市消防局清水消防署に配備されました。

こちらが、ショベルカーになります。もちろん、アームのアタッチメントも数種類搭載されています。

大規模災害用救助車。大規模災害時に、通常の震災対応の救助工作車と同様の働きをします。なお、車両はⅣ型の救助工作車に準じていますが、装備品は大きく異なり電気式救助機器を装備したERと空気圧式救助機器を搭載したARの2台一組で活動を行います。写真はERタイプ。

こちらはARタイプ。全国に3セットが配備され、うち1セットは静岡県浜松市消防局北消防署に配備されました。
他にも、無線中継車がありますがこちらは静岡県にも山梨県にも配備されなかったため、割愛させてもらいます。
このように特殊災害用の車両が国から無償で提供されることは喜ばしいことですが、配備先の消防本部は部隊用の人員を割かなければならない、緊急援助隊出動時には必ず出動しなければならないなど、負担が大きくなる側面も持っています。
人が少ない消防本部では、提供を断らなければならない事態になる可能性もあります。
無償提供の良し悪しも含めて、今後の消防の課題の一つになっていくと考えられます。
長文になりましたが、初更新はこれで終わります。ここまでお読みいただき、ありがとうございました~