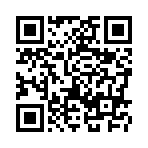2013年11月30日
救急車 その3
こんばんは。今回は救急車 その3です。
その3では、その1及びその2で紹介した、トヨタ並びに日産以外の救急車を紹介します。

札幌ボデーが販売している救急車はトライハートと呼ばれ、1992年に札幌市消防局との共同開発で誕生しました。高床キャンターをベースにすることで悪路の走破にも優れ、またトラックベースから室内空間の広さを実現しました。
1992年以降5代目キャンターから7代目キャンターまでのモデルが使用されていましたが、8代目キャンターが登場する際にエアサスのモデルが消滅するため、2008年からはいすゞエルフエアサス車をベースのものに変わりました。
なお、乗員定数は10名と国内高規格救急車では最大の人数を乗せることができます(なお3代目ハイメディックは8名)
写真は長野県諏訪広域消防本部の車両で7代目キャンターをベースにしています。
ちなみに、国産高規格救急車でトラックベースで販売しているものは、現在このトライハートのみとなっています。

三菱自動車が1997年に登場させた高規格救急車がディアメディックです(写真は島田市消防本部の車両。更新済み)
上記トライハートと同様にキャンターをベースにしていますが、短尺のボディを使用し最少半径4.9mという小回りを実現しました。東京消防庁などでも導入されましたが、2002年にキャンターのフルモデルチェンジに伴い生産終了となりました。

帝国繊維が発売していた救急車はオプティマと呼ばれていました。こちらはディアメディックに比べ車体長が長く、正にトラックベースの救急車というものでした。現在はほとんどが廃車になっており、予備車として残っている車両も少なくなってきています。

いすゞ自動車は、1995年にトラックベースのスーパーメディックを発売していました。こちらはいすゞエルフをベースとした車両で、トライハートやオプティマに比べ横に広い印象の車両でした(写真は三島市消防本部の車両。更新済み)

なお、低床と高床の2車種がありましたが、乗り心地などは悪いようです(写真は富士市消防本部の車両。更新済み)

トラックベースで最大級と言えば、東京消防庁が導入したスーパーアンビュランスが思い浮かびます。
こちらは1台目(すでに更新済み)、2台目ともに三菱ふそうグレート(2台目はスーパーグレート)をベースにしており、傷病者の収容数も高規格救急車などよりはるかに大きいものとなっています。なお、東京消防庁には現在2台が在籍しており、第2方面隊ハイパーレスキューに2台目が、第8方面隊ハイパーレスキューには3台目(いすゞギガベース)が配備されています。
この他にも、マイクロバスをベースとした救急車が存在し、消防本部所属車両では東京消防庁第3方面隊ハイパーレスキューの車両と愛知県知多中部広域事務組合消防本部に配備されています。

こちらは病院のドクターカー。規模の大きい病院では、ドクターカーやNICU(新生児集中治療)としての車両で導入されることが多く、消防ではあまり見られないマイクロバスベースの救急車がいたりします。なお、最近では搬送を救急車にし、初期治療で医師が同行するケースが多くなってきたため、医師と初期治療設備を運ぶためだけのドクターカーが増えてきています。これらの車両はセダンタイプやステーションワゴンの車両またはRV車ベースの車両が多く、小回りが利く点ではマイクロバスなどに比べて優れています。
以上で、その1~その3まで特集しました救急車についての説明を終わります。
次回は、化学工場や規模が大きい油火災などで活躍する化学車を特集します。では
その3では、その1及びその2で紹介した、トヨタ並びに日産以外の救急車を紹介します。

札幌ボデーが販売している救急車はトライハートと呼ばれ、1992年に札幌市消防局との共同開発で誕生しました。高床キャンターをベースにすることで悪路の走破にも優れ、またトラックベースから室内空間の広さを実現しました。
1992年以降5代目キャンターから7代目キャンターまでのモデルが使用されていましたが、8代目キャンターが登場する際にエアサスのモデルが消滅するため、2008年からはいすゞエルフエアサス車をベースのものに変わりました。
なお、乗員定数は10名と国内高規格救急車では最大の人数を乗せることができます(なお3代目ハイメディックは8名)
写真は長野県諏訪広域消防本部の車両で7代目キャンターをベースにしています。
ちなみに、国産高規格救急車でトラックベースで販売しているものは、現在このトライハートのみとなっています。

三菱自動車が1997年に登場させた高規格救急車がディアメディックです(写真は島田市消防本部の車両。更新済み)
上記トライハートと同様にキャンターをベースにしていますが、短尺のボディを使用し最少半径4.9mという小回りを実現しました。東京消防庁などでも導入されましたが、2002年にキャンターのフルモデルチェンジに伴い生産終了となりました。

帝国繊維が発売していた救急車はオプティマと呼ばれていました。こちらはディアメディックに比べ車体長が長く、正にトラックベースの救急車というものでした。現在はほとんどが廃車になっており、予備車として残っている車両も少なくなってきています。

いすゞ自動車は、1995年にトラックベースのスーパーメディックを発売していました。こちらはいすゞエルフをベースとした車両で、トライハートやオプティマに比べ横に広い印象の車両でした(写真は三島市消防本部の車両。更新済み)

なお、低床と高床の2車種がありましたが、乗り心地などは悪いようです(写真は富士市消防本部の車両。更新済み)

トラックベースで最大級と言えば、東京消防庁が導入したスーパーアンビュランスが思い浮かびます。
こちらは1台目(すでに更新済み)、2台目ともに三菱ふそうグレート(2台目はスーパーグレート)をベースにしており、傷病者の収容数も高規格救急車などよりはるかに大きいものとなっています。なお、東京消防庁には現在2台が在籍しており、第2方面隊ハイパーレスキューに2台目が、第8方面隊ハイパーレスキューには3台目(いすゞギガベース)が配備されています。
この他にも、マイクロバスをベースとした救急車が存在し、消防本部所属車両では東京消防庁第3方面隊ハイパーレスキューの車両と愛知県知多中部広域事務組合消防本部に配備されています。

こちらは病院のドクターカー。規模の大きい病院では、ドクターカーやNICU(新生児集中治療)としての車両で導入されることが多く、消防ではあまり見られないマイクロバスベースの救急車がいたりします。なお、最近では搬送を救急車にし、初期治療で医師が同行するケースが多くなってきたため、医師と初期治療設備を運ぶためだけのドクターカーが増えてきています。これらの車両はセダンタイプやステーションワゴンの車両またはRV車ベースの車両が多く、小回りが利く点ではマイクロバスなどに比べて優れています。
以上で、その1~その3まで特集しました救急車についての説明を終わります。
次回は、化学工場や規模が大きい油火災などで活躍する化学車を特集します。では
2013年11月28日
救急車 その2
こんにちは。前回に引き続き、今回も救急車の続きです。
前回トヨタの救急車の説明をしましたが、日産の救急車の紹介です。
・パラメディック
パラメディックは日産が作った高規格救急車です。1992年にアトラス20をベースに製作されましたが、1995年にアトラス20がいすゞからのOEMとなったため、日産オリジナルのアトラス顔からいすゞエルフ顔に変わりました。

マイナーチェンジ後の初代パラメディック(写真は浜松市消防局のもの。現在は更新済み)。国産高規格救急車としては初めてのトラックベースの車両でした。
そして、これと並走して1994年に登場したのがパラメディックⅡです。パラメディックはトラックベースのため室内空間の確保はできたものの、車体が大きく乗り心地が悪く搬送患者に影響を及ぼすこともありました。そのため、ワンボックスベースの高規格救急車として登場したのが本車です。

こちらがパラメディックⅡ(写真は三島市消防本部の車両)。4ナンバーのキャラバンでギリギリのスペースを有効活用しています。なお、高規格救急車の中では一番最少の車両であり、今でもこの車両より小さい高規格救急車はいません。
そして、パラメディックも1998年にフルモデルチェンジします。
今までパラメディックⅡとパラメディックの2車種で販売していたものを、フルモデルチェンジを機に両者を統合しパラメディックで統一しました。

こちらが2代目パラメディック(写真は静岡市消防局の車両)。正面はエルグランド、後ろはキャラバンの車体を使用した合造車で、ジャンボタクシーなどにもこの車体が流用されました。なお、パラメディックⅡもそうですが一部はいすゞにOEMとして供給され、スーパーメディック(パラメディックⅡのOEMはスーパーメディックⅡ)として販売されていました。

こちらがスーパーメディック(写真は静岡市消防局のもの。更新済み)。パラメディックとほぼ同じですが、車両屋根部の表記や装備ホイールの違いなど少ない点で違いがあります。
なお、日産の高規格救急車はマイナーチェンジをしているものの現在もこの2代目パラメディックを販売しており、国産高規格救急車としてはモデルとして一番長く販売されています。
・2B車両
トヨタと同じく、日産にも2Bタイプの救急車がいます。

E24キャラバンを使用した2B救急車。高規格救急車登場以前は、このタイプがかなりいました。写真は湖西市消防本部の車両(更新済み)

こちらが後期型タイプ。キャラバンホーミーの車体を使用したタイプで、現在でも予備車や病院の搬送車両として生き残っているものがいます(写真は磐田市消防本部の車両。更新済み)
以上で日産救急車勢の紹介を終わります。次回も救急車ネタでその他のメーカーの救急車を紹介します。
前回トヨタの救急車の説明をしましたが、日産の救急車の紹介です。
・パラメディック
パラメディックは日産が作った高規格救急車です。1992年にアトラス20をベースに製作されましたが、1995年にアトラス20がいすゞからのOEMとなったため、日産オリジナルのアトラス顔からいすゞエルフ顔に変わりました。

マイナーチェンジ後の初代パラメディック(写真は浜松市消防局のもの。現在は更新済み)。国産高規格救急車としては初めてのトラックベースの車両でした。
そして、これと並走して1994年に登場したのがパラメディックⅡです。パラメディックはトラックベースのため室内空間の確保はできたものの、車体が大きく乗り心地が悪く搬送患者に影響を及ぼすこともありました。そのため、ワンボックスベースの高規格救急車として登場したのが本車です。

こちらがパラメディックⅡ(写真は三島市消防本部の車両)。4ナンバーのキャラバンでギリギリのスペースを有効活用しています。なお、高規格救急車の中では一番最少の車両であり、今でもこの車両より小さい高規格救急車はいません。
そして、パラメディックも1998年にフルモデルチェンジします。
今までパラメディックⅡとパラメディックの2車種で販売していたものを、フルモデルチェンジを機に両者を統合しパラメディックで統一しました。

こちらが2代目パラメディック(写真は静岡市消防局の車両)。正面はエルグランド、後ろはキャラバンの車体を使用した合造車で、ジャンボタクシーなどにもこの車体が流用されました。なお、パラメディックⅡもそうですが一部はいすゞにOEMとして供給され、スーパーメディック(パラメディックⅡのOEMはスーパーメディックⅡ)として販売されていました。

こちらがスーパーメディック(写真は静岡市消防局のもの。更新済み)。パラメディックとほぼ同じですが、車両屋根部の表記や装備ホイールの違いなど少ない点で違いがあります。
なお、日産の高規格救急車はマイナーチェンジをしているものの現在もこの2代目パラメディックを販売しており、国産高規格救急車としてはモデルとして一番長く販売されています。
・2B車両
トヨタと同じく、日産にも2Bタイプの救急車がいます。

E24キャラバンを使用した2B救急車。高規格救急車登場以前は、このタイプがかなりいました。写真は湖西市消防本部の車両(更新済み)

こちらが後期型タイプ。キャラバンホーミーの車体を使用したタイプで、現在でも予備車や病院の搬送車両として生き残っているものがいます(写真は磐田市消防本部の車両。更新済み)
以上で日産救急車勢の紹介を終わります。次回も救急車ネタでその他のメーカーの救急車を紹介します。
2013年11月22日
救急車 その1
こんにちは。救助工作車の記事を更新後、仕事が忙しくなり更新している暇がありませんでした。申し訳ありません。
さて、今回解説する救急車は、誰でも知っている車両です。火を消すポンプ車や救助作業を行う救助工作車よりも出動回数が多く、首都東京を管轄する東京消防庁では48秒に1件、救急車1台当り1日7.7件出動しているほどです。
日本における最初の救急車は1931年に大阪に配備され、それ以降傷病者を病院に運ぶ任をしています。1991年以前は、救急隊が病院に傷病者を搬送するのを主としていましたが、法律の関係上救急隊員が医師でないため医療活動を行うことはできませんでした。そのため、1分1秒を争う場合病院に着いてからでは手遅れというケースも多く、また助かっても後遺症などの社会復帰に問題があるなどの点もありました。
そこで、1991年に救急救命士法が制定され、医師の指示の下、医療処置が行えるようになりました。これ以降救急車には順次医療処置ができる設備が搭載され、それまでの2B(ベッドが2つ)型救急車の他に高規格救急車と言う分類ができました。輸液や除細動(心肺蘇生)、薬剤投与など医療処置が行えることで、救命率は上がりました。また、これまでの2B救急車も高規格用の設備を搭載したものが登場し、こちらは準高規格救急車と言う分類になっています。
ポンプ車やタンク車などは消防車を作るメーカーが車両メーカーが作った車を艤装しますが、救急車はこれらのメーカーの他に車両メーカー自身が自社の車を艤装して作っている場合があります。
ではその1では、トヨタ車両を紹介します。
・ハイメディック(HIMEDIC)
ハイメディックはトヨタ自動車が作っている高規格救急車です。1991年の救急救命士法制定直後は、日本に高規格救急車がいなかったため、ベンツやフォードの車両をベースにした救急車がいましたが、車体が大きいが故狭い道の日本には使い勝手が悪く、また気候などから車両故障もしばしばありました。そして1992年に国産高規格救急車初として登場したのがハイメディックです。

こちらが初代ハイメディックです(写真は静岡市消防局のもの。廃車済み)。100系ハイエースをベースに、屋根をかさ上げし、室内高を確保しました。またエンジンもハイエースオリジナルのものではなく、セルシオ用のV形8気筒エンジンを搭載。独特な音をするサイレンと前面に書かれたエンジン形式を示すV8が特徴でした。現在はほとんどが廃車になっており、残っている車両も予備車として配備され、他は海外に譲渡され活躍されています。

1997年にフルモデルチェンジされ、新しく登場した2代目ハイメディックです(写真は静岡市消防局のもの)。初代は高規格として設備・車両性能を重視しすぎたあまりコストがかかり、車両価格が高くなってしまったことを踏まえ、コストダウンと使いやすさ向上を目標に作られました。その2で紹介する日産パラメディックと並び全国各地に配置され、また小回りできるように日本の救急車で初の4WSを採用しました。また、後期モデルでは輝度不足で実現が難しいとされていたLED赤色灯を小糸製作所と共同制作し、視認性が大幅にアップしました。こちらも現在は予備車に降格している車両が多いですが、地方都市ではまだ現役で活躍しているところもあります。

2006年に100系ハイエースがフルモデルチェンジするのとほぼ同時期にモデルチェンジしたのが3代目ハイメディックです(写真は峡南広域行政組合消防本部のもの)。2代目の4WS機能を省き、コストダウン化及び室内の空間確保がされました。こちらも登場当時から多くの消防本部で配備され、今も第一線で活躍しています。

こちらは大月市消防本部の3代目ハイメディック。赤いラインの配置が独特で、俗称ではウルトラマンとも言われているほどらしいです。

2010年にマイナーチェンジをした3代目ハイメディック(写真は富士五湖消防本部のもの)。フロントライトやバンパーの形状が変わりました。またフロントライトもHIDにできるようオプションが追加されました。

比較写真(共に富士市消防本部のもの)。向かって左側がマイナーチェンジ後の車両、右がマイナーチェンジ前の車両です。フロントライトの形状が違うのが分かります。
・2B車両(トヨタ)
高規格とは別に、昔からある普通救急車のことを指します。高規格救急車では値段が高すぎたり、狭い道などに入る際に車両サイズが大きすぎるなどの問題から、現在でも販売されています。なお、設備機器類は高規格に準じたものであるため、医療処置は高規格救急車と同様のことが行えます。しかし、ほとんどの消防本部が高規格救急車を入れているため、現存している車両はほとんどが予備車や病院の搬送車ばかりです。

100系ハイエースを使用した2B救急車は、高規格救急車が登場する以前に多く使われていたうちの1台のため、現在残っている古いタイプの中でも多い方に分類されます(写真は湖西市消防本部のもの。廃車済み)

こちらは後期型の100系ハイエースをベースとした2B救急車(写真は富士宮市消防本部のもの)

ハイメディックが1997年に2代目に移行したのち、2B救急車もフルモデルチェンジされました。写真のトヨタレジアスエースがベースの車両は、現存している2B救急車の中でも最も多いタイプと思われます(写真は富士市消防本部のもの。廃車済み)

2006年にハイメディックがフルモデルチェンジされたのに伴い、2Bも再びモデルチェンジました。車両外観はほとんど3代目ハイメディックと同じものにされています(写真は浜松市消防局のもの)
その1は以上で終わります。その2では日産の車輌を紹介したいと思います。では
さて、今回解説する救急車は、誰でも知っている車両です。火を消すポンプ車や救助作業を行う救助工作車よりも出動回数が多く、首都東京を管轄する東京消防庁では48秒に1件、救急車1台当り1日7.7件出動しているほどです。
日本における最初の救急車は1931年に大阪に配備され、それ以降傷病者を病院に運ぶ任をしています。1991年以前は、救急隊が病院に傷病者を搬送するのを主としていましたが、法律の関係上救急隊員が医師でないため医療活動を行うことはできませんでした。そのため、1分1秒を争う場合病院に着いてからでは手遅れというケースも多く、また助かっても後遺症などの社会復帰に問題があるなどの点もありました。
そこで、1991年に救急救命士法が制定され、医師の指示の下、医療処置が行えるようになりました。これ以降救急車には順次医療処置ができる設備が搭載され、それまでの2B(ベッドが2つ)型救急車の他に高規格救急車と言う分類ができました。輸液や除細動(心肺蘇生)、薬剤投与など医療処置が行えることで、救命率は上がりました。また、これまでの2B救急車も高規格用の設備を搭載したものが登場し、こちらは準高規格救急車と言う分類になっています。
ポンプ車やタンク車などは消防車を作るメーカーが車両メーカーが作った車を艤装しますが、救急車はこれらのメーカーの他に車両メーカー自身が自社の車を艤装して作っている場合があります。
ではその1では、トヨタ車両を紹介します。
・ハイメディック(HIMEDIC)
ハイメディックはトヨタ自動車が作っている高規格救急車です。1991年の救急救命士法制定直後は、日本に高規格救急車がいなかったため、ベンツやフォードの車両をベースにした救急車がいましたが、車体が大きいが故狭い道の日本には使い勝手が悪く、また気候などから車両故障もしばしばありました。そして1992年に国産高規格救急車初として登場したのがハイメディックです。

こちらが初代ハイメディックです(写真は静岡市消防局のもの。廃車済み)。100系ハイエースをベースに、屋根をかさ上げし、室内高を確保しました。またエンジンもハイエースオリジナルのものではなく、セルシオ用のV形8気筒エンジンを搭載。独特な音をするサイレンと前面に書かれたエンジン形式を示すV8が特徴でした。現在はほとんどが廃車になっており、残っている車両も予備車として配備され、他は海外に譲渡され活躍されています。

1997年にフルモデルチェンジされ、新しく登場した2代目ハイメディックです(写真は静岡市消防局のもの)。初代は高規格として設備・車両性能を重視しすぎたあまりコストがかかり、車両価格が高くなってしまったことを踏まえ、コストダウンと使いやすさ向上を目標に作られました。その2で紹介する日産パラメディックと並び全国各地に配置され、また小回りできるように日本の救急車で初の4WSを採用しました。また、後期モデルでは輝度不足で実現が難しいとされていたLED赤色灯を小糸製作所と共同制作し、視認性が大幅にアップしました。こちらも現在は予備車に降格している車両が多いですが、地方都市ではまだ現役で活躍しているところもあります。

2006年に100系ハイエースがフルモデルチェンジするのとほぼ同時期にモデルチェンジしたのが3代目ハイメディックです(写真は峡南広域行政組合消防本部のもの)。2代目の4WS機能を省き、コストダウン化及び室内の空間確保がされました。こちらも登場当時から多くの消防本部で配備され、今も第一線で活躍しています。

こちらは大月市消防本部の3代目ハイメディック。赤いラインの配置が独特で、俗称ではウルトラマンとも言われているほどらしいです。

2010年にマイナーチェンジをした3代目ハイメディック(写真は富士五湖消防本部のもの)。フロントライトやバンパーの形状が変わりました。またフロントライトもHIDにできるようオプションが追加されました。

比較写真(共に富士市消防本部のもの)。向かって左側がマイナーチェンジ後の車両、右がマイナーチェンジ前の車両です。フロントライトの形状が違うのが分かります。
・2B車両(トヨタ)
高規格とは別に、昔からある普通救急車のことを指します。高規格救急車では値段が高すぎたり、狭い道などに入る際に車両サイズが大きすぎるなどの問題から、現在でも販売されています。なお、設備機器類は高規格に準じたものであるため、医療処置は高規格救急車と同様のことが行えます。しかし、ほとんどの消防本部が高規格救急車を入れているため、現存している車両はほとんどが予備車や病院の搬送車ばかりです。

100系ハイエースを使用した2B救急車は、高規格救急車が登場する以前に多く使われていたうちの1台のため、現在残っている古いタイプの中でも多い方に分類されます(写真は湖西市消防本部のもの。廃車済み)

こちらは後期型の100系ハイエースをベースとした2B救急車(写真は富士宮市消防本部のもの)

ハイメディックが1997年に2代目に移行したのち、2B救急車もフルモデルチェンジされました。写真のトヨタレジアスエースがベースの車両は、現存している2B救急車の中でも最も多いタイプと思われます(写真は富士市消防本部のもの。廃車済み)

2006年にハイメディックがフルモデルチェンジされたのに伴い、2Bも再びモデルチェンジました。車両外観はほとんど3代目ハイメディックと同じものにされています(写真は浜松市消防局のもの)
その1は以上で終わります。その2では日産の車輌を紹介したいと思います。では