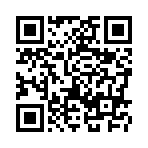2013年09月07日
タンク車
こんにちは。
前回は「火を消す車」ということで、2種類の内のポンプ車に関しての記事を書かせていただきましたが、今回はもう一方のタンク車に関して書かせていただきます。
タンク車はポンプ車と基本的に同じ役割をしますが、大きな違いは水槽を積んでいるところです。
一般的に火を消すには水が必要です。しかし、到着場所に常に水利があるわけではなく、その場合その場所にもっとも近い水利から水を持ってこなければなりません。これでは、水を出すのに大幅に時間がかかってしまいますし、初期放水ができません。そのため、初期放水をするために水槽付きの車両が考えられ、水槽付きポンプ車「タンク車とも」と言われるようになりました。
タンク車にはⅠ型とⅡ型があり、Ⅰ型にはポンプ車同様ホイールベースの違いからⅠ-AとⅠ-B型の2種類に分けることができます。
まずはⅠ型から。Ⅰ型は水槽容量1500リットル以上の車両を規定しています。

こちらはⅠ-A型のタンク車です(写真は島田市消防本部金谷消防署川根南分遣所のタンク車)。I-A型は主にホースカー無の車両ですが、補助金の関係上ホイールベース3m以上、A-2級以上のポンプを搭載しています。

なお、近年では見栄えや機能性重視のため、すべてシャッター方式にする車両が増えています(写真は静岡市消防局千代田消防署しずはた出張所のタンク車)

こちらはⅠ-B型のタンク車です(写真は富士市消防本部西消防署のタンク車)。Ⅰ-B形はホースカーを搭載している点がⅠ-A型と大きく異なる点になります。ちなみにこちらも補助金の関係上、ホイールベース3.5m以上、A-2級以上のポンプを搭載しているという国の規格に則った車両がほとんどです。
ちなみにホースカーとは、名前の通りホースを搭載した車両です。火災現場でホースを延長する際に人間が一度に持てるホースの束には限界があります。そこでホースカーにホースを搭載し、それを延長することによって無駄な手間をなくすことができるのです。
お次はⅡ型。Ⅱ型は水槽容量2000リットル以上の車両を規定しています。

Ⅱ型タンク車(写真は甲府市広域行政組合消防本部中央消防署のタンク車)。ホースカーを搭載しているもの、していないもの関わらず、2t以上の水槽を搭載していればⅡ型に分類されます。ポンプの機能はⅠ型同様A-2級以上のポンプを搭載していることが前提です。

こちらもⅡ型のタンク車(写真は浜松市消防局中消防署のタンク車)。5t水槽を搭載するため、車体は2t水槽の車両よりも大きなもの(7t~8tシャーシ)を使用しています。
タンク車の基本的な説明は以上です。では少しだけ派生型を見てみましょう。

こちらは磐田市消防本部磐田消防署豊田分遣所にいるⅠ-A型タンク車。ホースカーは搭載していませんが、救助資機材も搭載しており、交通事故事案などにも対応できます。

こちらも同様、Ⅰ-A型のタンク車。前面表記もある通り、こちらは純粋に救助工作車として運用していますが、元々はタンク車なので火災事案にも出動ができると思われます。ちなみに所属は静岡市消防局湾岸消防署庵原分署の車両で、元は静岡市消防局追手町消防署のタンク車として運用されていました(途中の湾岸PR運用は除く)
以上で、タンク車の説明を終わります。次回は・・・様々な分野で人命救助を行い、憧れのオレンジ服の隊員が乗る救助工作車をご説明します
前回は「火を消す車」ということで、2種類の内のポンプ車に関しての記事を書かせていただきましたが、今回はもう一方のタンク車に関して書かせていただきます。
タンク車はポンプ車と基本的に同じ役割をしますが、大きな違いは水槽を積んでいるところです。
一般的に火を消すには水が必要です。しかし、到着場所に常に水利があるわけではなく、その場合その場所にもっとも近い水利から水を持ってこなければなりません。これでは、水を出すのに大幅に時間がかかってしまいますし、初期放水ができません。そのため、初期放水をするために水槽付きの車両が考えられ、水槽付きポンプ車「タンク車とも」と言われるようになりました。
タンク車にはⅠ型とⅡ型があり、Ⅰ型にはポンプ車同様ホイールベースの違いからⅠ-AとⅠ-B型の2種類に分けることができます。
まずはⅠ型から。Ⅰ型は水槽容量1500リットル以上の車両を規定しています。

こちらはⅠ-A型のタンク車です(写真は島田市消防本部金谷消防署川根南分遣所のタンク車)。I-A型は主にホースカー無の車両ですが、補助金の関係上ホイールベース3m以上、A-2級以上のポンプを搭載しています。

なお、近年では見栄えや機能性重視のため、すべてシャッター方式にする車両が増えています(写真は静岡市消防局千代田消防署しずはた出張所のタンク車)

こちらはⅠ-B型のタンク車です(写真は富士市消防本部西消防署のタンク車)。Ⅰ-B形はホースカーを搭載している点がⅠ-A型と大きく異なる点になります。ちなみにこちらも補助金の関係上、ホイールベース3.5m以上、A-2級以上のポンプを搭載しているという国の規格に則った車両がほとんどです。
ちなみにホースカーとは、名前の通りホースを搭載した車両です。火災現場でホースを延長する際に人間が一度に持てるホースの束には限界があります。そこでホースカーにホースを搭載し、それを延長することによって無駄な手間をなくすことができるのです。
お次はⅡ型。Ⅱ型は水槽容量2000リットル以上の車両を規定しています。

Ⅱ型タンク車(写真は甲府市広域行政組合消防本部中央消防署のタンク車)。ホースカーを搭載しているもの、していないもの関わらず、2t以上の水槽を搭載していればⅡ型に分類されます。ポンプの機能はⅠ型同様A-2級以上のポンプを搭載していることが前提です。

こちらもⅡ型のタンク車(写真は浜松市消防局中消防署のタンク車)。5t水槽を搭載するため、車体は2t水槽の車両よりも大きなもの(7t~8tシャーシ)を使用しています。
タンク車の基本的な説明は以上です。では少しだけ派生型を見てみましょう。

こちらは磐田市消防本部磐田消防署豊田分遣所にいるⅠ-A型タンク車。ホースカーは搭載していませんが、救助資機材も搭載しており、交通事故事案などにも対応できます。

こちらも同様、Ⅰ-A型のタンク車。前面表記もある通り、こちらは純粋に救助工作車として運用していますが、元々はタンク車なので火災事案にも出動ができると思われます。ちなみに所属は静岡市消防局湾岸消防署庵原分署の車両で、元は静岡市消防局追手町消防署のタンク車として運用されていました(途中の湾岸PR運用は除く)
以上で、タンク車の説明を終わります。次回は・・・様々な分野で人命救助を行い、憧れのオレンジ服の隊員が乗る救助工作車をご説明します
Posted by エルピープルップルン at 08:50│Comments(0)
│消防